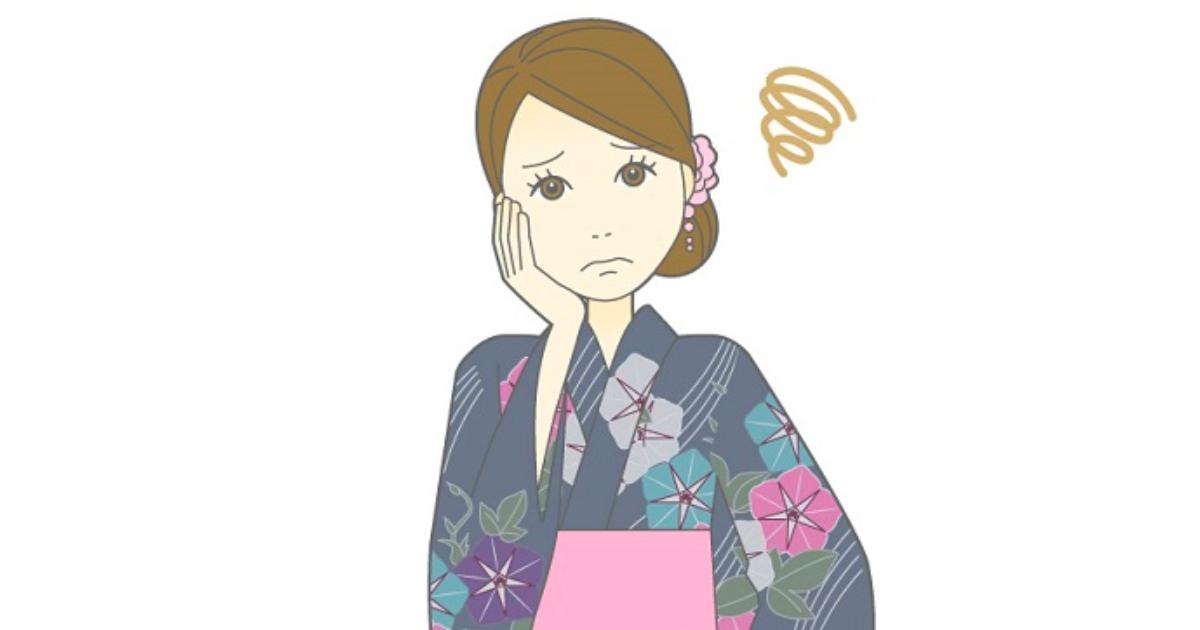浴衣に限らず着物は男女問わず「右前」と言いますが、上になるのはどちらなのか?
着付けをしてもらう時には気にもならないものですが、浴衣のように自分で着る場合には、「右が上?」「右が前?」「前って上?それても手前?」など、わからなくなってしまいますよね。
でも、大丈夫です。覚え方は簡単。
右前とは右手が胸元に入るように着る
これだけ覚えておけばいいのですが、タブーや豆知識も含めて右前とはどういうことかをご紹介します。
そもそも着物って何?なにが着物?
現代で「着物」と呼ばれるものは、大きく3種類あります。
- 衣類全般:洋服も含め身につけるもの全般を意味する
- 和服全般:洋服・洋装に対しての和装・和服全般
- 外出着向けの和装:留袖、振袖、訪問着、小紋など
※この場合には、パジャマやルームウェアにあたる「浴衣」や作業着にあたる「作務衣」などは含まれません
今回は、浴衣なども含めた和装全般を意味する着物に当てはまる「右上」についてのお話です。
着物や浴衣は右左のどっちが上?右前とは?

着物は男女問わず「右前」で着ます。
前述したように、右前とは右手が胸元に入るように着ることです。
上の画像でわかるように、右手で胸元に小物などをいれられるように着るのが正解です。
慣れない時、久々に着る時に「右前」で混乱してしまうのは、「前」の意味が紛らわしいからですよね。
- 位置関係としての前:表、上
- 時間的な意味での前:先、手前
着物で「右前」というのは、時間的な意味での前にあたります。言い換えれば、先に右側を体に巻く、右が手前になることを意味します。
注意ポイント
左前は死装束の着せ方ですので、くれぐれもご注意ください
着物や浴衣の和服はどうして右前?
日本の着物は呉服(ごふく)とも呼ばれます、3世紀中頃中国南部の「呉の国」の衣服(呉服)が伝えられたことに由来します。素材や繊維の織り方が伝わり、デザインや着方などは日本独自の進化をするのですが、当初日本では、右前や左前の決まりはなく、それぞれ自由に着ていたそうです。
その後、719年に奈良時代の朝廷が「衣服令(えぶくりょう)」にて、「どのような身分のものもすべて右前にするように」と定めました。
古来日本では「左が上位」と考えられていました。話が少しずれますが、お雛様の左大臣と右大臣では左大臣の方が位が上になります。右前、つまり右側(右前身頃)を先に(手前に)体に巻くと、左側(左前身頃)が表側、上側にくるようになりますね。
※右前には、中国に倣った、右手が使いやすくなり戦い向きなど、諸説あります
関連
死装束を左前に着せる理由にも、諸説あります。
・現生と死後は真逆の関係にある
・亡くなると仏様となり位が上がる
・お釈迦さまが亡くなられた時に左前で着ていた など
さいごに
着物や浴衣を着る際の右前とは右手が胸元に入るように着ることです。他にも、「他人から見てアルファベット小文字のy」などの覚え方もありますが、いずれにしてもわかりやすく忘れない表現で覚えておくと混乱は防げますよ。
反対に左前できると死装束の着方となりますので、間違えないように気をつけましょうね。
こちらもCHECK
-

-
浴衣脇の下が丸見え!理由や対処方法、おすすめインナーは?
浴衣を着て外出前に鏡を覗いてみたら、なんと脇の下の下着が丸見え状態。 どうしたものかとクラクラしますね。 今回は、そもそもどうして女性の着物や浴衣の脇の下があいているのか、オススメのインナーや、上手な ...
続きを見る
こちらもCHECK
-

-
浴衣の着崩れ防止対策と直し方は?襟 帯 裾 初心者に出来る事は?
浴衣は着るのは簡単というけれど、着崩れたら自分で直せるか心配、、 直したつもりが不要な箇所を引っ張ってさらにおかしくなったり、、どこをどう直していいのかわからなかったり、だからと言ってキツく締めすぎて ...
続きを見る
こちらもCHECK
-

-
浴衣でトイレの仕方は?男性、女性、裾のまくり方、お手洗いでの注意点は?
手軽に着ることのできる浴衣ですが、悩ましいのはお手洗い、トレイの行き方ですね。 今回は、浴衣でのトイレの行き方について男女別に、裾のまくり方やお手洗いでの注意事項等をまとめました。着物や浴衣を着なくて ...
続きを見る
こちらもCHECK
-

-
浴衣には下駄以外でもいいの?サンダル・スニカー・ビーサン・クロックスは?
不慣れな下駄は歩くのが心配!浴衣には下駄以外のものを合わせたい! せっかくの浴衣、足元も自由に楽しみたい! わかります、、この気持ち。私が若い頃には浴衣には下駄。小中学生までであれば、ビーチサンダルも ...
続きを見る