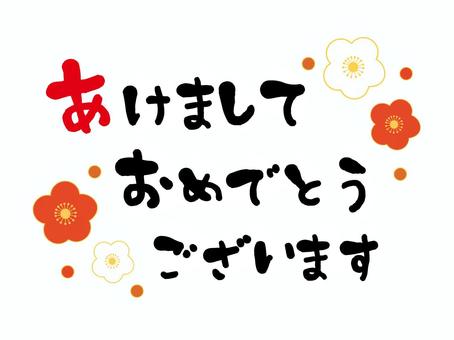喪中期間だとお正月のお祝いが控えますが、子どもが楽しみにしていることもあるので悩ましいこともありますね。。
今回は、子供が楽しみにしているお年玉や、おせち料理やお雑煮などの食べ物のことと、子ども用の喪中はがきや年賀状などの基本的な考え方をご紹介します。
喪中期間のお年玉はどうする?

喪中は「身内が亡くなって悲しいためお祝い事をする気持ちになれません。身を慎んでいます。」という期間のことです。
お年玉は現代の子供にとっては年始の特別なお小遣いでしかありませんが、お年玉の「玉」は「魂」に通じており、発端はお金ではなく年神様へのお供えである「お餅」、お祝い事の一環でした。昔からの日本の慣習として、お正月には正月飾りをつけ、鏡餅をお供えし、家に恵みを与えてくれる年神様をおもてなしし、お供え後に鏡餅のお下がりを家族全員で食べ、お年玉に宿った年神様の魂(力)をいただくことになっていたのです。
そう考えると、喪中期間はお祝いに通じるお年玉を渡すことは控えた方が良いでしょう、という発想になっていますね。
ただ、子供達にとっては年に1回の楽しみです。今年は喪中だからお年玉はありませんよ、というのは可哀想ですよね。年中行事のひとつと捉え、「お年玉」をあげてもいいでしょうし、気になる場合には表書きを変えるといいでしょう。
・おもちゃ代
・本代
・文房具代 など
お年玉袋も、紅白水引きの熨斗袋ではなく、おめでたい感の少ないポチ袋などを利用するといいでしょう。100円ショップなどで、可愛らしいものがたくさんあります。
本来であれば、白無地や地味な袋がいいのでしょうが、相手は子どもです。せっかくもらう年に1度の特別なお小遣いですから、あまり深く考えなくてもいいでしょう。
喪中期間のおせち料理やお雑煮はお祝い料理か?
おせち料理やお雑煮も、年神様へのお供えした食べ物を、お供え後に一緒にいただくという神聖な物だったのです。
特におせち料理は、今でこそお正月の年1回だけになっていますが、元々は中国からきた五節句(人日、上巳、端午、七夕、重陽)全ての日にお供えする料理であり、1つ1つの料理に家族繁栄や無病息災などの願いが込められています。基本的にはお祝い料理ですから、喪中の料理としては相応しくありません。
ただ、毎年正月にはおせちとお雑煮が習慣だったので無いのは寂しい、という場合は、お祝い料理としてでなく、質素な方法や食材で用意すれば問題ないのではないかと思います。
・お祝いのイメージが強い鯛(めでたい)や紅白かまぼこなどを避ける
・重箱でなくお皿に盛り付け
・お屠蘇は避ける
おせち料理は購入すると豪華なものもありますが、喪中の年は自分たちの好きな物だけばら売りを買ってきたり家で作るなど、普段のおかずと同様の感覚で食べれば問題ないでしょう。
ちなみに我が家の数年前の喪中では、おせち料理の中で食べたい種類だけ作って食べた記憶があります。栗きんとん、黒豆、煮しめ、田作り程度でした。
お雑煮についても、確かにお餅は昔からお祝い事や特別の日の料理で、年神様のお供えのお下がりとしていただく食べ物でした。
昔は白米やもち米は高価な食べ物で一般庶民には手の届かないものだったため餅の代わりに里芋を雑煮に入れて食べていたのですが今では餅は高価ではありませんし、ご飯やパンと同じような感覚で食べられるものです。
お祝いの食事という概念を外して質素に普通の食事として食べればお雑煮も問題ないでしょう。
子供の喪中はがきや年賀状は?

喪中期間は、基本的にオトナの話です。忌中であればまた別ですが、子供の年賀状はあまり深く考えなくてもいいでしょう。亡くなった時期や、子どもの気持ちを優先させるといいでしょう。
忌中や、家族の悲しみが深い場合には、年賀状ではなく普通のお手紙がオススメです。
子どもの場合、自分が年賀状を出したのに相手から年賀状が来ないと、いじめや陰口の原因になったりもします。大人であれば、寒中見舞いなど他の方法もありますが、子どもの場合には「冬休み」期間を考慮する必要があります。クリスマスカードは冬休みのとの関係で難しいし、寒中見舞いだと学校が始まっている可能性が高いです。
年賀状ではなく、普通のお手紙を冬休み期間中に出すよう、お手伝いするといいでしょう。この場合も、「喪中」や「○○が亡くなった」などの言葉は避ける方がいいでしょう。受け取る相手も子どもであることを配慮しましょう。
あけましておめでとうございます。
年賀状ありがとう。うれしかったです。
出すのが遅くなってごめん。
今年も仲良くしてね。
ねんがじょう、ありがとう。
まいにちさむいね。
がっこうははじまったら、またいっしょにあそぼうね。
ことしもなかよくしてね。
子どもがある程度大きくなり、喪中を理解する年齢であれば、あなた方の喪中ハガキをそのまま使い、差出人の夫婦の名前の横に子どもの名前を書かせて投函してもいいでしょう。
喪中はがきの差出人名は、基本的に親のみです。子供の名前は連名にしません。
こちらもCHECK
-

-
喪中はがきに子供の名前も連名で入れる?子供の友達への年賀状は?
身内に不幸があり喪中の場合、喪中はがきに子どもの名前を連名でいれるのか、子どもの年賀状はどうするのかは悩ましいところです。 今回は、喪中はがきに子どもの名前をどうするかなどを、ご紹介します。
続きを見る
こちらもCHECK
-

-
喪中期間の子供の年賀状は?返事は年賀状、寒中見舞い?文例
喪中の場合、子どもの年賀状はどうすればいいでしょうか。 大人は11月頃に喪中はがきを出して相手にお知らせしますが、子どもの場合は喪中はがきをだしません。お友達に年賀状を出していいのか、届いた年賀状に返 ...
続きを見る
喪中期間であることは子供に伝える?
お葬式などで身近な人が亡くなったことはわかっていても、年齢によってはそれがどういうことなのか、理解していない可能性もあります。
小さなうちは別ですが、小学校に入ったら、喪中とはどういうことなのか教えてもいいかもしれませんね。
身近な人や大切な人が亡くなると悲しいこと、悲しい期間はお祝い事をしないこと、「あけましておめでとう」は言わないこと、お祝い事をしないから華やかなお節料理がないことなど、子供の年齢に合わせて教えるといいでしょう。