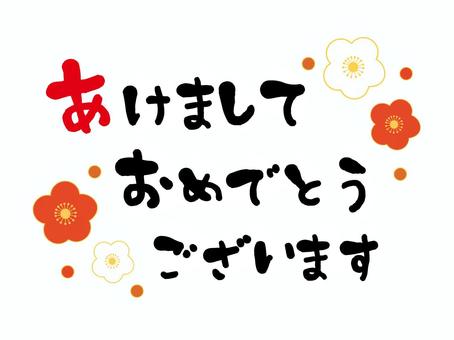喪中の場合、子どもの年賀状はどうすればいいでしょうか。
大人は11月頃に喪中はがきを出して相手にお知らせしますが、子どもの場合は喪中はがきをだしません。お友達に年賀状を出していいのか、届いた年賀状に返事を出していいのか、子どもでも寒中見舞いにする方がいいのか、、、今回は、喪中期間の子供の年賀状の考え方についてご紹介します。
自分たちが喪中の場合、子供の年賀状はどうする?

自分たちは喪中の場合、故人との関係性や亡くなった時期にもよりますが、一般的には子どもは年賀状を出しても構いません。
子どもからみた喪中の範囲は?
まずは、喪中の範囲です。一般的な喪中の範囲とは、2親等。子供から見た2親等は祖父母、自分たちの親です。
子供から見た親(1親等)、兄弟姉妹(2親等)の場合、心情的にお祝い気分にはならないかと思うので、対象から外しています
自分たちにとっては、1親等である親が亡くなり、家族の悲しみが深い場合には、年賀状は控えてもいいでしょう。
自分たちの祖父母(2親等)が亡くなった場合には、子どもにとっては3親等です。子どもの気持ちが落ち着いており、年賀状を楽しみにしている場合には、出しても構わないでしょう。
子どもから見た、叔父や叔母(自分たちの兄弟姉妹)やひいおじいちゃん・ひいおばあちゃん(自分たちの祖父母)は、一般的な喪中の範囲からは外れます。かわいがってもらっていて、子供の悲しみが深いような場合は、楽しい気分ではないでしょうから、年賀状を出す出さないは、子供の気持ちを優先しましょう。
喪中の期間は?
喪中というと1年といイメージがありますが、現実的にはその期間喪に服すことは、現代ではほぼあり得ません。1年間は、お正月は控えますが、故人との関係によって数ヶ月単位で、実生活は元に戻ります。
【一般的な喪中期間】
・配偶者、親:12〜13ヶ月
・子ども:12〜13ヶ月
・兄弟・姉妹・祖父母:3ヶ月〜6ヶ月
忌中(仏式で49日)であれば、年賀状は控える方がいいですが、それ以降は子どもと話をして決めるといいでしょう。子どもの年齢にもよりますが、身内を亡くした時の新年の迎え方などを、教えることができます。
喪中期間の子供の年賀状の考え方

最終的には子供の気持ちに寄り添うことが大切ですが、子供の年賀状は次のように考えてみるといいでしょう
・普通に年賀状を出す、届いた年賀状にも返事を書く
・届いた年賀状にだけ年賀状で返事を書く
・普通のお手紙を送る
・クリスマスカードを送る
・寒中見舞いにする
大人の場合、2親等である祖父母が亡くなると、同居か別居かで判断が異なっても構いませんが、子供の場合には、同居も別居もあまり関係ありません。
子供が年賀状を出したり、もらうことを楽しみにしているのであれば、出しても構わないでしょう。
ただ、子どもから見た2親等の祖父母は、自分たちの親(1親等)です。同居、別居関わらず、自分たちは喪中ですし、悲しみが深い場合には、いくら自分の子どもが楽しみにしているといっても、年賀状を用意したり、手伝う気分にもならないかもしれません。このような場合には、身内に不幸があった場合の、新年の迎え方を教えてもいいように思います。子供の年齢にもよりますが、、
年賀状が難しい場合には、普通のお手紙にして、ハガキで送るといいでしょう。
喪中に届いた子供あての年賀状の返信は?
年賀状、寒中見舞い、普通のお手紙のいずれでも、できるだけ新学期開始前に相手に届くように送るといいでしょう。
子どもの場合、自分が年賀状を出したのに相手から年賀状が来ないと、いじめや陰口の原因になったりもします。「喪中」であることを周りも理解しているのであればいいですが、他の家の子がどのように受け止めるかまではわかりません。。
年賀状の返信として出す場合には、新年の挨拶の他、もらった年賀状のお礼、近況報告など一言添えるといいでしょう。
あけましておめでとうございます。
年賀状ありがとう。うれしかったです。
出すのが遅くなってごめん。
今年も仲良くしてね。
喪中における寒中見舞い子供向け文例は?
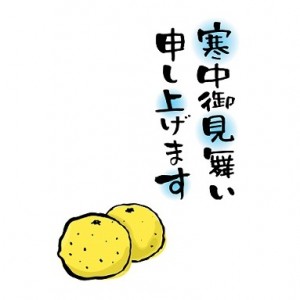
年賀状ではなく、寒中見舞いで送る場合には、松の内明けになります。関東では1月7日が松の内なので、1月8日以降に届けばいいのですが、地域によっては松の内は15日です。16日以降に届けるとなると、もうすっかり学校も始まっていて、逆に説明がつかないかもしれませんね、、
子どもの学年によっては、「かん中みまいもうしあげます」となり、書いている本人も、もらう側も、なんのことかわからないこともあります。その場合には、普通のお手紙として書いてもいいでしょう。その場合には、日にちも気にせず送ることができますね。
相手が年賀状をもらえなかったことを気にしている可能性もあるので、年賀状を出さなかった場合には、学校でお友達に年賀状のお礼と、○○が亡くなったから年賀状が出せなかったということを、口頭で先に伝える方が良さそうです。
ねんがじょう、ありがとう。
まいにちさむいね。
がっこうははじまったら、またいっしょにあそぼうね。
ことしもなかよくしてね。
子供の友達が喪中なら年賀状はどうする?
子どものお友達が喪中であることを知っている場合には、故人との関係や亡くなった時期にもよりますが、年賀状ではなくお手紙やクリスマスカードを送ってもいいでしょう。
ただ、自分の家が喪中でも子どもが年賀状を出すように、お友達の家が喪中でも子どもは年賀状を出す可能性もあります。お友達の親に子供の年賀状をどうするか聞いてみてもいいかもしれませんね。
「うちの○○が、年賀状を出したいと言っているのですが、喪中だと伺っておりまして、、、」という感じで、子ども同士の話として聞く分には、相手の気分を害する可能性は低いでしょう。
さいごに
子どもの年齢や、故人との関係、子どもの気持ち次第ではありますが、親が喪中でも子どもがお友達に年賀状を出すことには、さほど神経質にならなくてもいいでしょう。
クリスマスカードという方法もありますが、クリスマス前に届けるには学校がまだ冬休みに入っていない可能性もありますし、だからといってギリギリに送るとクリスマスを過ぎてしまうかもしれません。
寒中見舞いであれば、学校が始まってしまうこともあります。
年賀状を避けたいのであれば、普通のお手紙として送ることもできます。ただ、お正月期間が、年賀状以外は多少遅配する可能性もありますので、年明け早々に送るか、年末ギリギリに発送するといいでしょう。
それぞれ一長一短あるので、それを理解しつつお子さんとどうするか話し合って決めてくださいね。