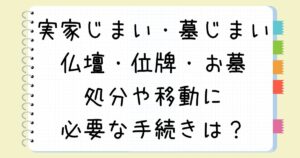四十九日法要の際に納骨するのが一般的ですが、お墓がない場合や、もう少し遺骨を傍に置いておきたい場合など、納骨しないで遺骨を自宅安置するケースもあります。
その場合の、考え方や置き方、注意点などをまとめておきます。
四十九日法要の後も遺骨を自宅安置するのは良くないの?
四十九日法要を終えても遺骨を自宅に置いておくことは良くない」、という方もいらっしゃいますが、実際どうなのでしょうか?
遺骨を自宅で保管することに法的に問題はある?
遺骨を自宅で保管することには法的にはなんの問題もありません。
【遺骨に関する法律は?】
「墓地・埋葬に関する法律」で定められているのは、「遺骨を埋葬・納骨をする場合、自治体が認めた場所にする」ことです。
自宅の庭や思い出の場所に遺骨を埋葬することは認められませんが、自宅で保管することは違法でがありません。
お墓がない、お墓を準備中、お墓はあるけれどまだそばに置いておきたい、、、遺骨を自宅で保管したい理由がどんなものであれ、何の問題もないのですよ。
遺骨を自宅に置いていたら成仏できない?
仏教では「納骨しないと成仏できない」といった考え方はありません。
日本において一般的に、「成仏する」とは「亡くなった方が極楽で生まれ変わる」ことを意味します。そのため、故人の霊魂があの世に行けずにこの世を彷徨っている状態を「成仏していない」と言います。
成仏の考え方は、仏教でも宗派によって異なります。浄土真宗では、亡くなるとすぐに成仏すると考えますし、それ以外の宗派でも四十九日で成仏するとの考え方が一般的です。
つまり、遺骨の保管場所、安置場所と成仏できるかどうかには、なんの関係もありません。
遺骨を自宅安置するのは良くないと言われる理由は?
法的にはなんの問題もないのに、「家に置いておくのは良くない」と言われるのはなぜなのでしょうか。
縁起が悪い?
「縁起が悪い」とは、何かよくないことがおこりそうな様子、凶兆であるさまを意味します。
仏教では即日、あるいは四十九日で成仏しますし、「縁起」自体が気持ちのよりどころの問題ですから、周りがどうこういってもイヤな人はイヤだし、根拠がないので気にしない人は気にしないものです。
成仏できない?
成仏できない、供養されない、との考え方もあるようですが、こちらの方が仏教の考え方に反しているので、気にする必要はありません。
遺骨は不浄?
仏教では、死は穢れ(けがれ)と捉えることはありませんので、不浄にはあたりません。
遺体は土に還すべき?
過去には、日本でも土葬の頃の考え方でしょうか。土葬の頃には、早々に土葬しないとご遺体が傷むので必要な手順でもありました。そんな土葬でも、土に還るには数十年から100年程度かかると言われています。
現在は火葬が基本です。火葬し、骨壷に納め、基本的にお墓などに納骨します。火葬した遺骨の場合は、土に還るまで数百年かかるとも言われています。 高音で火葬されると、骨の表面がセラミック上に変化するので、土に還りにくくなるそうです。
納骨しても、土に還るのは随分先ですから、数十日、数年単位で急ぐ話でもありませんし、「べき」論の根拠もありません。
違法行為?
先述の通り、遺骨の自宅保管や自宅安置は違法行為ではありません。納骨は当然のようにされることが多いですし、「自宅庭から白骨化した遺体を発見」などの事件もありますので、誤解や勘違いしているのかもしれませんね。
遺骨を自宅供養・手元供養する方法と注意点
自宅供養の場合には、お墓の購入費用や維持管理費用がかかりませんし、お墓参りも不要です。
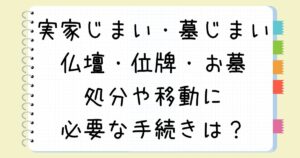
自宅供養する方法
骨壷の一部もしくは全部を自宅に安置し供養することを、自宅供養や手元供養とも言います。
自宅供養の方法に決まり事などはありませんので、仏壇においたり、棚などに骨壷スペースを確保しましょう。
ただし、火災や地震等の自然災害時に破損や紛失する可能性もありますし、自身が亡くなった後の扱いに家族や親族が困ることもあります。どこかのタイミングで納骨や散骨するなど、決めておくといいかもしれませんね。
遺骨の分骨して手元供養する方法
分骨とは
手元におき供養したくても、大きい遺骨、大きい骨壷のまま安置するのが難しい場合には、分骨という方法もあります。2つ以上の骨壷に、故人の遺骨を分けて収めることで、法で認められた供養方法です。
【分骨の例は?】
- 兄弟で別のお墓を作るため、親やご先祖さまの遺骨を分骨する
- お墓が遠方にあるため、分骨し自宅近くのお墓に納骨する
- 浄土真宗遺骨を宗祖への畏敬の意味として本山に分骨する(浄土真宗)
- 手元供養のために分骨する
分骨する方法
分骨の理由はそれぞれでかまいませんが、いずれにしても分骨には「分骨証明書」が必要になります。
【分骨証明書とは?】
- 故人の氏名や亡くなった年月日、性別、本籍、住所、分骨する理由、分骨した後の埋葬地など、分骨に関する情報が記載されます
- 分骨する時だけでなく、複数の場所に埋葬する場合にも必要になります
- 火葬場、役所、納骨した寺院や霊園などで発行してもらいます
火葬場で分骨する場合
火葬時に分骨が決まっている場合には、あらかじめ葬儀会社や火葬場の職員に分骨する旨と、分骨する数を伝えておきます。火葬場に、分骨する分の骨壷を持参すれば、その場で分骨することが可能ですし、その他の手続きも不要です。
分骨証明書は、火葬場から発行してもらうことができます。
納骨前に分骨する場合
納骨前で、自宅供養・手元供養している骨壷から分骨するには、火葬を行なった火葬場(斎場)や、役所に分骨証明書の発行申請をする必要があります。
分骨の作業は、業者に依頼しても構いませんし、家族で行なうこともできます。
納骨後に分骨する場合
納骨後に分骨する場合には、寺院や霊園にまず相談してみましょう。
墓石の移動の他、開眼供養や閉眼供養が必要なこともあります。供養方法や宗教、宗派、寺院によって考え方も、かかる費用も異なります。
分骨後の手元供養の方法
分骨後、一部だけ手元供養することもできます。
小さな骨壷を用意する
そのまま手のひらサイズにしたような、コンパクトサイズの骨壷が人気です。

ペンダントヘッドなどのアクセサリーに加工する
故人への想いを込めて身につけられるアクセサリーにも加工できます。大切な人を亡くした寂しさや喪失感から「まだ離れがたい」「そばにいて欲しい」という思いを持つ方に選ばれています。

ダイヤモンドへの加工
ダイヤモンドは炭素なので遺骨から加工することが可能です。ただ、純度の高いダイヤモンドを生成するためには高い技術が必要となり、やや高額になります。
ちなみに、合成ダイヤモンドの作り方についてはこちらのページが参考になりますよ。
→アルゴダンザダイヤモンドの製造工程・製作期間
他にも、キーホルダーに加工したり、小さなカプセルに入れたりすることもできます。ご自身の納得する形で手元供養できるといいですね。
自宅供養に祭壇を使っても良いの?
葬儀後、四十九日法要が終わるまでは、中陰壇(ちゅういんだん)や後飾りと呼ばれる故人を祀る祭壇があります。
宗教や宗派によって考え方は異なりますが、一般的には、四十九日法要を終えて納骨したら処分や葬儀会社に返却したりします。
納骨まで時間がかかる場合には、そのまま祭壇に祀っていても問題はありません。そのまま保管しておき、お盆や法事の際に使用することもできます。
ただ、仏壇ではありませんし、段ボールなどで簡易的な作りのものもありますので、あとはご自身の判断となるでしょう。
自宅にお墓を作ることはできる?
上述の通り、遺骨の自宅保管や自宅安置は違法ではありませんが、自宅の庭などに埋葬・納骨すると違法です。
カビの発生に注意
遺骨は、湿気を吸収しやすいため、保管状況によってはカビが発生する場合もあります。
火葬場で骨壷に納めて遺骨は滅菌状態ですが、その後なんらかの理由でカビ菌が混入したり、骨壷内に結露が起こったりすると、カビが発生しやすくなります。
一度遺骨にカビが生えてしまうと、保管するにも、納骨するにも手入れが必要になりますので、注意が必要です。
埋葬許可証は残しておく
火葬後、火葬場や役所から「埋葬許可証」が渡されます。この埋葬許可証がないと、後に納骨したくなった時にかなり手間がかかります。くれぐれも紛失などしないよう、気をつけましょう。
*****
お墓への納骨は、しなければならないものでも、しないと何か不幸なことがあるわけでもありません。大切な人の遺骨ですから、納得するまで手元で供養しても構わないのですよ。
ただ、保管方法を間違えるとカビが生えたり、破損したりと、より悲しみが深くなる可能性もあります。
分骨し、一部だけ手元供養することで、いつでもそばにおいておくこともできます。あなたにとって、一番いい方法がみつかることを願っています。