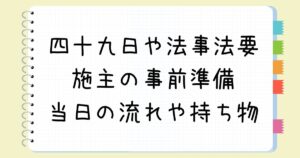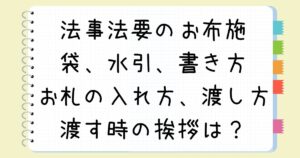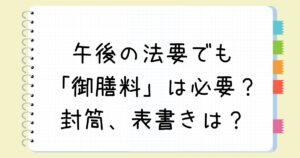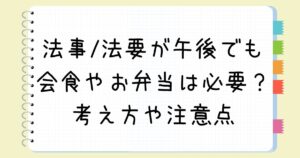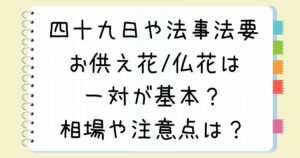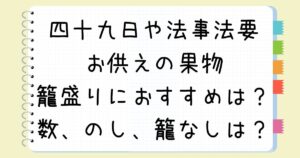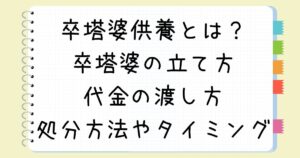四十九日法要と同日に行うことが多い納骨。納骨法要の費用相場、石屋さん(石材店)への支払い方法、封筒の種類や表書き、お礼の渡し方、そもそも納骨は自分でできるのか、、、など、納骨法要に関する基本的な考え方をまとめておきます。
納骨法要のお布施相場は?
納骨法要(納骨式)のお布施の相場は、次のように言われています。
【納骨法要のお布施相場は?】
- 四十九日法要 相場:3〜5万円程度
- 納骨法要 相場:3〜5万円程度
- 開眼供養 相場:3〜5万円程度 ※ お墓を新しく建てた場合
※ お墓が寺院から離れている場合には、別途お車代をお渡しすることもあります
※ 霊園や納骨堂に納める場合には別途費用がかかります
その他に、お墓にお供えするお花やお線香、納骨後に会食をする場合には会食代がかかります。
地域や宗教、宗派、菩提寺との関係によっても異なりますし、お墓を新しく建てるなどで、納骨法要だけ行う場合と、四十九日法要などどいっしょに執り行う場合でも多少異なります。
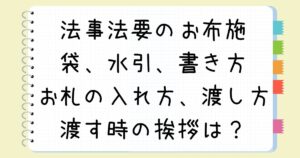
石屋さん(石材店)への納骨費用の相場は?
石屋さん(石材店)の合計支払相場は7万円程度と言われています。
【石材店に払う納骨費用の相場は?】
- 納骨費用:2〜3万円程度
- 彫刻料(墓誌への名入れ費用):3〜5万円程度
石材店の納骨費用
石屋さん(石材店)への納骨費用(納骨の作業工賃)は2〜3万円程度と言われています。
中には、納骨費用と墓誌への名入れの合計金額で出しているところもありますが、その場合7万円前後と言われています。
石材店の納骨費用のほとんどは人件費です。
すでにあるお墓を開閉するだけで、そんなにかかるの? と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、安全かつスムーズに納骨してもらうための費用です。高すぎるものではありません。
石材店に依頼することで、
・管理事務所等への手続き等の前準備をしてもらえます
・高価で重量があり、壊れやすい墓石を安全に移動してもらえます
・納骨スペース(カロート)の目地をはがして蓋を開けて、再度蓋を閉めて目地を埋めてもらえます
納骨後、目地を埋めるのには場合によって20~30分程度作業が発生します。自分で納骨する場合には、その作業や準備も必要です。納骨後すぐに、会食などへ向かうわけにもいきません。。
石材店によっては、お墓周りの清掃もしてもらえます。なんだかんだで、2〜3時間かかる細かな作業から、プロフェッショナルな作業までをお願いしている費用なのです。
墓誌への名入れ費用(彫刻料)
墓誌に、戒名、俗名、没年月日、享年などを彫刻してもらう費用(彫刻料)が別途かかります。相場は3〜5万円程度と言われています。
【墓誌とは?】
墓誌とは、埋葬されている先祖の戒名や没年月日などが彫刻されている石板のことです。一般的には、お墓の右側か左側に建てられます。
現在は、サンドブラストという、研磨用の砂と空気を混ぜたものをコンプレッサーで墓石に噴射して彫刻する方法で行うのが一般的なので、文字数に関わらず一律料金になっていること多いです。
彫刻作業は、納骨法要前に済ませるのが一般的です。納骨日が決まったら早めに依頼しましょう。少なくても、2週間程度は時間の余裕を持ちましょう。
石屋さん(石材店)への納骨費用の渡し方は?
石屋さんに渡す納骨費用の渡し方は、通常の支払いと同様に考えて構いません。
石屋さん(石材店)への納骨費用の封筒は?
寺院へのお布施と同様「不祝儀袋」と考えるかもしれませんが、ごく普通の無地の白封筒で構いません。
石材店への納骨費用は、納骨に関わる作業への対価です。寺院や僧侶への謝礼であるお布施とは異なります。
石屋さん(石材店)への納骨費用の表書きは?
上述の通り、納骨に関わる作業への対価ですから、表書きは不要です。味気ないので何か書きたい場合には、「納骨費用」等でいいでしょう。
石屋さん(石材店)への納骨費用の渡し方は?
石材店にもよりますが、一般的には納骨終了後に現金での支払いか、銀行振込になるでしょう。
納骨や名入れ(彫刻)を発注した際に、支払い方法等を確認しておきましょう。
納骨で石屋さんにお心付け・寸志は必要?金額は?
ここで気になるのが、石材店へのお礼、お心付け、「寸志」が必要か、、ということになります。
要は、チップですね。日本ではチップの習慣はありませんが、昔からの慣習で、今でもお心付け・寸志 を渡すことが多いです。
石材店の方へのお心付け・寸志は、3,000〜5,000円程度が相場と言われています。納骨後、納骨費用の支払いの際や、お墓から退去時にお渡ししましょう。
ただ、最近では、サービス量も含めた料金設定となっているとの考え方もあり、必ずしも渡さなければならないものではありません。地域慣習や石材店との関係にもよるでしょう。
納骨を自分でするのは可能なのか?
納骨は通常、寺院や石材店に頼むことが多いのですが、自分で納骨することも可能です。
納骨をするために必要な手続きや手順は?
納骨する大まかな手順は次の通りです。
【納骨の手順】
- 事前連絡をする
- 埋葬許可証を墓地の管理者に提出する
- 納骨する
事前連絡をする
墓地には、寺院と公営霊園、民営霊園、共同墓地などがあります。
いずれにしても納骨日が決まったら、墓地の管理者に納骨の日時を事前に伝えます。
寺院のお墓であれば寺院に、公営霊園や民営霊園であれば管理事務所に、共同墓地であれば管理委員会や役所・役場などに連絡します。その際に、当日、あるいは事前に提出の必要な書類、当日の準備物なども確認しましょう。
【納骨当日に必要なもの】
- 墓地の管理事務所用:埋葬許可証、お墓の使用許可証、印鑑、手数料 など
- お墓用:お供えの花、線香、マッチ、ロウソク、数珠 など
埋葬許可証を墓地の管理者に提出する
墓地に納骨する際には、埋葬許可証を墓地の管理者に提出しなければなりません。
「墓地、埋葬等に関する法律」第14条にて定められています。そのため、自分で納骨する場合、石材店などに依頼する場合のどちらにしても必要です。
【埋葬許可証の発行は?】
埋葬許可証は、火葬場で発行してもらえることが多いです。火葬場や地域によっては、役所や役場で発行してもらうこともあります。
通常は、骨壷ケースなどに一緒に入れて、火葬後で納骨に必要であることを説明を受け、渡されます。紛失した場合には、市町村役場で再発行の手続きが必要です。
寺院で納骨する場合
寺院の場合には、葬儀や法要を営む際に納骨をどうするか決めるのが一般的です。
日程を決め、埋葬許可証を提出すればいいので、さほど手間はかかりません。手順なども、寺院と相談できます。
公営霊園、民営霊園、共同墓地などの場合
公営霊園等の場合には、墓地の管理事務所等に納骨の連絡をした際に、当日の流れも確認しましょう。
一般的には、墓地の管理事務所で埋葬許可証の提出やお墓の使用許可証の提示、その他必要な書類があれば、記入、押印、手数料の支払いなどを行います。
納骨する
自分納骨する場合
自分で納骨をする場合には、管理事務所と確認した手順通りに進めましょう。
管理事務所等の立ち合いがある場合には、前日や当日早めに行き、立ち合いの時間までにお墓を掃除しておきましょう。
管理事務所等の立ち合いがないのであれば、納骨前に掃除をしてもいいでしょう。
納骨室(カロート)に複数の骨壺がある場合、古いものを奥へ移動して、今回納める骨壺を手前に置きます。
納骨後は、納骨スペースをきちんと元の状態に戻し、お参りします。
納骨式を行う場合
納骨式の一般的な流れは以下の通りです。家族だけで行う場合には施主の挨拶は不要です。
【納骨式の一般的な流れ】
- 施主の挨拶
- 新しくお墓を建てた場合には読経(開眼供養)
- 納骨
- 僧侶の読経
- 遺族の焼香
- 施主の挨拶
納骨をお寺や石材店に依頼すべきケースとは?
必要な手続きを踏めば、自分で納骨することができますが、難しいケースもあります。
【石材店に依頼した方がいいケース】
- 新しくお墓を建てる場合
- 既にお墓があっても、管理者が寺院の場合
- 墓誌などの名入れが必要な場合
- お墓の開閉が自分では難しい場合
新しくお墓を建てる場合
新しくお墓を建てる場合には、僧侶に開眼供養をしてもらう必要があります。そのため、寺院を通さないのは現実的には難しいでしょう。
お墓を建てただけでは魂が入ったとはいえず、開眼供養を営むことで、故人の魂の拠り所となるお墓になるのです。その開眼供養を行うには、僧侶に読経していただく必要があります。
【開眼供養とは?】
開眼供養(かいげんくよう)、あるいは 入魂式、魂入れといった供養を行うことで、お墓はお墓として、仏壇は仏壇として、位牌は位牌として故人の魂の拠り所となります。開眼供養をしなければ、お墓はただの石であり、仏壇はただの棚であり、位牌はただの板、、、というように仏教では考えます。
仏像を作る際に、最後に眼を描き込むことで仏像に魂が入り完成すると考えたことに由来し、お墓や仏壇、位牌を新たに購入した際に執り行われるようになりました。
※ 石材店ではお墓を購入していますので、最初の納骨費用はサービスだったり、格安で対応していただけることもあります。
既にお墓があっても、管理者が寺院の場合
既にお墓がある場合でも、お墓の管理者が寺院であれば、寺院に埋葬許可証を提出することになります。そのため、寺院に納骨法要を依頼せず、自分たちで納骨するのは現実的に難しいと言えます。
また、寺院によってはその墓地で工事ができる業者「指定石材店」があることも多いです。指定石材店がある場合には、原則として自分での納骨ができません。
市営などの公営霊園や共同墓地の場合には、指定石材店はないでしょう。民営霊園の場合には、ほぼ指定石材店があると思ってもよさそうです。
墓誌などの名入れが必要な場合
納骨の際、故人の戒名や没年月日等を墓石や墓誌に名入れします。
彫刻するタイプの場合は、自分で彫ることができないため、石材店に依頼することになります。
新しいお墓を建てる場合には、開眼供養が必要ですが、墓誌の名入れには開眼供養は必要ありません。納骨だけし、墓誌に名入れしないのであれば、自分で納骨することも可能です。
お墓の開閉が自分では難しい場合
納骨スペースの開閉は、一般的にかなりの力を要します。また、墓石は欠けたり割れたりしやすいので、扱いに注意も必要です。動かす時、置く時などに、ぶつけたり、勢いよく置いたりしないよう、慎重に扱う必要があるのです。
他にも、納骨スペースがどうなっているのかを、事前に確認しておく必要もあります。
・納骨室(カロート)がどこにあるか(お墓の下か、線香を建てる石のところか等)
・納骨室がお墓の下の場合、拝石(石蓋)の周りがコーキングされていないか
・納骨方法(骨壺のまま納骨するのか、晒しの袋に移し替えるか、骨だけ入れるのか等)
納骨スペースの仕様は、だいたい決まっていますが、家のお墓がどれなのかは自分で確認しなければなりません。
コーキングされている場合には、納骨前にコーキングを取り除き、納骨後に再度コーキングする必要があります。必要な道具も自分で持参する必要があります。
簡単な仕様になっていても、重たかったり、開けにくいこともあります。くれぐれも墓石を傷つけないよう、また自分もケガをしないよう気をつけましょう。
*****
納骨自体は自分ですることもできますが、実際には難しいです。
納骨する際には、納骨法要のお布施の他に、石材店への納骨費用や彫刻料がかかります。
石材店の方へお礼(お心付け・寸志)をお渡しする昔からの慣習も残っています。お心付け(寸志)は、必ずしも渡さなければならないものでも、渡さないとバチがあたるわけでも、作業が乱雑になるわけでもありません。あくまで気持ちの問題です。
納骨は、故人の葬儀の締めのようなものです。費用を払うのも、基本的には故人の家族です。それなりの出費にはなりますが、あまり頭を悩ませずに、最後の儀式を気持ちよく、つつがなく行えることを第一に考えてみましょう。