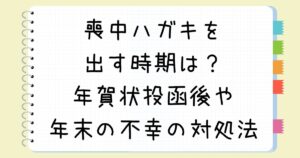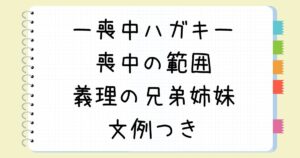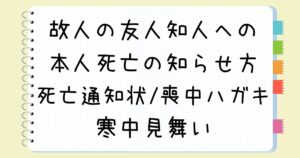一般には、喪中ハガキで故人の没年齢を記載する際には、「数え年」を用います。享年・行年・没年などの言い方もありますので、それぞれの考え方や書き方、計算方法をまとめておきます。
喪中はがきの年齢は「満年齢」と「数え年」どっち?
喪中はがきに記載する年齢は、基本的に「満年齢」と「数え年」のどちらを使っても構いませんが、「数え年」を用いることが多いようです。
昔の日本では、数え年による年齢計算でした。明治時代に満年齢を採用する法律が制定されましたが、それからもしばらくは、公的なもの以外は数え年が使われていました。
満年齢が民間まで広く普及したのは、昭和24年(1950年)制定の「年齢のとなえ方に関する法律」がきっかけです。現在の日常生活では、ほとんど満年齢を使用しています。
ただ、仏事や神事(七五三や厄年など)に関しては、数え年が残っています。
仏教では、母親の胎内で生を受けた時から命をいただいたと考えるため、十月十日を過ごし、出産時に1歳と数えます。そのため、位牌や墓誌、過去帳に刻まれる亡くなった時の年齢は「数え年」なのです。
その流れで、喪中はがきでも「数え年」を記載することが多いようです。
喪中はがきは、家ごとに用意します。例えば親が亡くなった際に、子である兄弟姉妹が独立していれば、それぞれの家で喪中はがきを用意します。
その際に、「数え年」や「満年齢」をそれぞれで使い分けると、場合によっては2歳ずれます。誤解や面倒にもなりかねませんので、特別な理由がなければ、あまり深く考えず一般的な「数え年」で揃えておくと間違いありません。
また、数え年の方が長生き感がでるというのも選ばれる理由の一つです。
「享年」「行年」「没年」の違いは?
喪中はがきや訃報では、享年・行年・没年といった表記を見かけます。その違いも、区別しておきましょう。
享年とは?
享年(きょうねん)とは、この世に生を受けてから亡くなるまでの年数を表す言葉で、一般には数え年を用います。
「享年」の「享(キョウ・うける)」には「ありがたく受け取る」という意味があります。上述の通り、仏教では、母親の胎内で生を受けた時から命をいただいたと考えるため、十月十日を過ごし、出産時に1歳と数える、数え年です。そのため、享年では、一般的に数え年を用いるのです。
「享年」という言葉そのものに、「生を受けてから亡くなるまでの年数」という意味が含まれますので、「享年○○」と「歳」をつけずに表記します。
ただ、最近では満年齢が標準化しているからか、「享年100歳でした」などと報道されることもあるので、「享年○○歳」という表記も誤りとはされません。
行年とは?
喪中はがきや墓誌などで、「行年」を使うこともあります。
「行年(ぎょうねん・こうねん)」とは、娑婆で修行した年数つまり、この世に生まれて何歳まで修行したかを意味します。そのため、一般的には満年齢の表記となり、「行年○○歳」と表記します。
没年とは?
似たような表記で「没年(ぼつねん)」もあります。「没」は亡くなったことを意味し、没年とは故人の亡くなった年をあらわす言葉です。ただし、この場合の「年」には、「年齢」と「年次」の両方で使うことができます。
- 没年〇〇歳:故人が亡くなった年齢を示す
- 没年2023年:亡くなった年を示す
喪中はがきは「享年」「行年」のどっち?
喪中はがきでは、「享年」「行年」のどちらも使えます。
どちらが正しいというものでもありません。寺院や地域によっても解釈が異なるため、菩提寺に確認すると間違いないでしょう。
喪中はがきに「享年」は必要?
喪中はがきでは、「享年」はつけてもつけなくても、どちらでも構いません。
喪中はがきでの年齢の表記はどれが正解?
こうなると、どれが正しい表記なのか、もうわけがわかりませんね。。。
喪中はがきの年齢表記に関しては、決まりもなければ、正しい表記法もないのです。
【満年齢85歳の場合】
◉満年齢で表記する
・85歳 ← 満年齢のみ表記
・行年85歳 ← 行年 + 満年齢+歳、行年の一般的表記法
・享年85歳 ← 享年 + 満年齢+歳、享年に満年齢をつけることもある
◉数え年で表記する
・87歳 ← 数え年のみ表記
・享年87← 享年 + 数え年、歳をつけない一般的表記法
・享年87歳 ← 享年 + 数え年+歳、現代的表記
・行年87歳 ← 行年 + 数え年+歳、行年に満年齢をつけることもある
同じ人の年齢なのに、満年齢と数え年では異なります。さらに、寺院や地域によって、享年、行年の使い方も異なります。どれか正解なわけでも、間違いなわけでもないので、ややこしいですがそういうものと割り切るしかありません。
相手に、故人の年齢を正確に伝えたい場合には、「享年○○(満○○歳)」という表記をなさる方もいらっしゃるようですが、これはもう個人(遺族)の判断ですね。。
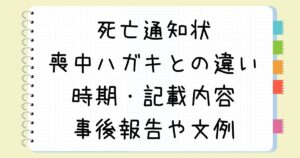
喪中はがきに年齢の表記は必要?
かなりややこしい年齢表記ですが、喪中はがきは、年始挨拶の欠礼をお知らせするものですから、故人の情報はなくてもいいのです。
年齢、故人の名前、続柄、いずれも記載しなくても構わないのです。
最近は、個人情報保護やプライバシーの観点からなのか、単にできる限りの手間を省きたいのか、他に理由があるのかないのかわかりませんが、、喪中ハガキの記載内容もシンプルなものが人気のようです。
ただ、喪中はがきで、初めて差出人の身内に不幸があったことを知る相手もいますので、続柄程度は記載しておく方が、双方にとって無駄のない情報となるでしょう。
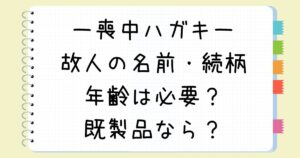
喪中はがきの年齢計算で注意すべきことは?
喪中はがきでは、満年齢えも数え年でもどちらでも構いません。
ただ、数え年の場合には、誕生日前後で計算方法が異なりますのでご注意ください。
・1月1日〜誕生日前:満年齢+2歳
・誕生日〜12月31日:満年齢+1歳
※ 数え年では、1月1日に1歳増えます
ある程度の年齢になると、正確な年齢がわからない方もいます。
私は、30代半ばから自分の歳がよくわからないなり、必要に応じて西暦で計算しているくらいです。。。私みたいな人は少ないでしょうが、自称満年齢には勘違いもありますので、年齢早見表などで確認することをオススメします。
なお、数え年を確認する場合には、「数え年」で検索しましょう。多くの年齢早見表は、「満年齢」表記になっています。
下記は、岡山県の茶屋町稲荷神社の早見表(2024年/令和6年)。干支なども1枚でわかるので便利です。PDFでタウンロードもできます。⇒ダウンロード(https://inari-jinja.com/downloa)
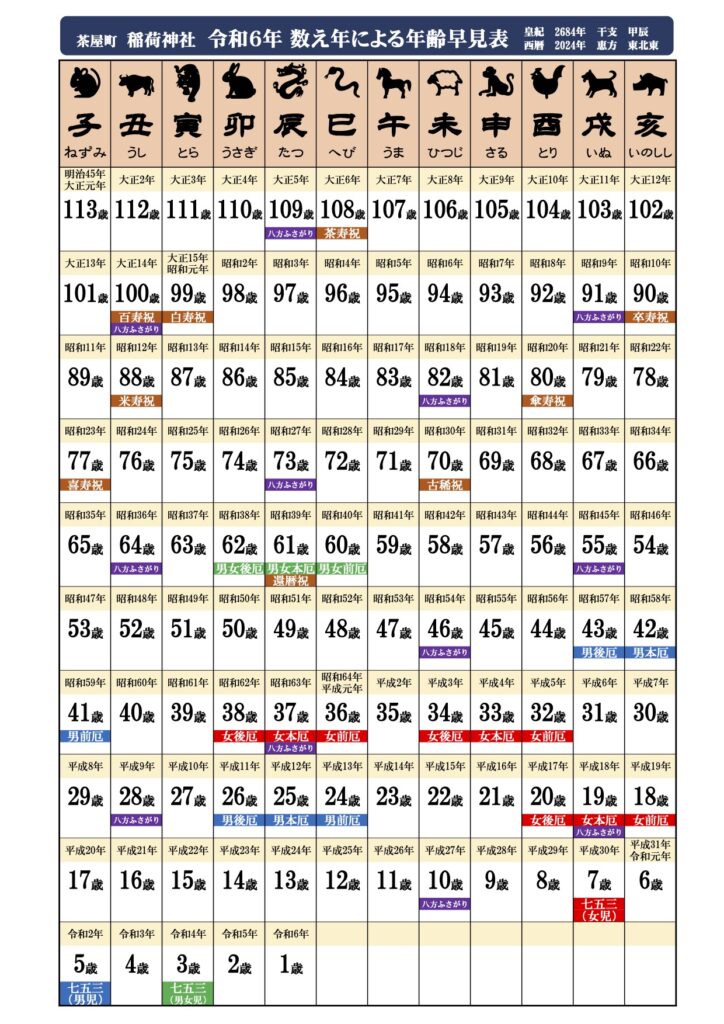
喪中ハガキでは、年齢は数え年でも満年齢でも構いません。また、年齢を記載しなくても問題はありません。
家や地域、寺院によっても考え方は異なりますので、気になる場合には菩提寺に確認するか、お葬式の時の会葬御礼や位牌、墓誌などを参考にするといいでしょう。