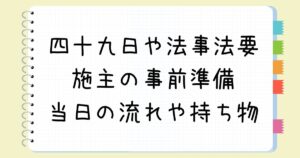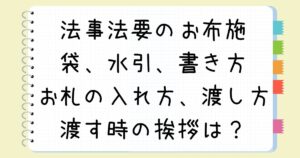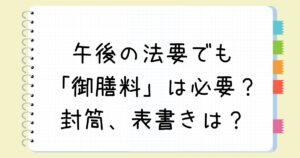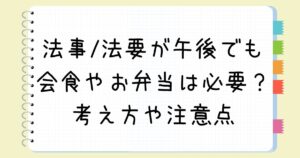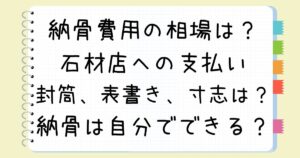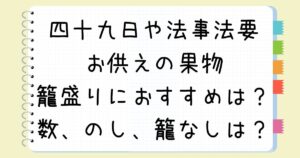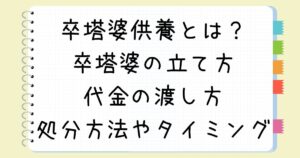四十九日法要や一周忌法要などでお供え花を寺院に持参する場合の、お供え花の用意の仕方や注意事項などをまとめておきます。
地域や家、寺院によっても考え方は異なりますが、参考になれば幸いです。
四十九日法要や一周忌でのお供えの花は?
四十九日法要や一周忌では、法要をどこで執り行うかによっても、考え方が異なります。
四十九日法要や一周忌法要の会場は?
四十九日法要やその後の年忌法要はを執り行う場所に決まりはありませんが、一般的には、次のような場所で行います。
【法事法要を営む場所】
- 寺院
- 家(自宅)
- セレモニーホール などの会場
法事法要のお供えの花は誰が用意する?
四十九日法要やその後の年忌法要では、お供え花を用意しますが、誰が用意するかは会場によっても異なります。
【お供え花を用意するのは?】
- 会場が寺院:施主が持参 or 寺院で手配
- 会場が自宅:施主が手配
- セレモニーホールなど:会場が手配 or 施主が持参
実際には、寺院で執り行うことが多いかと思われますが、ご本尊にお供えする花は、基本的には施主が持参します。
ただ、寺院にお願いすることもできますし、寺院側の手配が普通になっていることもあります。その場合には、金額を前もって確認し「御花代」をお渡しします。
いずれにしても、法要の日程を決める際に、用意するものは詳しく確認しておきましょう。
法事法要でのお供え花の相場や形態、種類は?
法事法要でのお供え花の相場は?
法事法要での、ご本尊へのお供え花は、5,000〜10,000円程度で考えておけばいいでしょう。
地域や家の慣習、寺院の考え方により異なる場合もありますが、その場合には相場ではなく、慣習に従う方が無難です。
法事法要でのお供え花の形態は?
お供え花の形態には、花束、籠花、アレンジメントなどがあります。
法事法要で、施主が用意するお供え花の形態は、花瓶に活ける普通の花束、切り花が多いです。最近は、そのまま飾ることができるアレンジメントも人気です。
【お供えの花を用意する時の注意点は?】
- 寺院の考え方や地域慣習もありますので、フラワーアレンジメントで用意する場合には、手配する前に寺院に確認する方がいいでしょう。
- 施主以外の列席者がお供え花持参する場合には、アレンジメントでも問題はありません。
寺院で営む場合には、寺院の花瓶に活けるので、花瓶の持参は不要です。花を注文する際に、法事法要用であることを伝えれば長さなどは調整してもらえます。
自宅で営む場合には、仏壇用の花瓶でも構いませんし、普段よりも大きな花になる場合には、お供え花に見合ったサイズの花瓶を用意しておきましょう。
法事法要のお供え花は一対?
法要のお供え花は、左右対称に飾れるように2セット用意する「一対」が基本ですが、必ずしも一対である必要はなく「一基」でも構いません。
法事法要のお供え花が「一対」であることに、宗教的に意味があるのは確認できませんが、「見栄えが良いため」という説があります。
見栄えの問題であれば、片側にだけお供えする「一基」でもご本尊や故人、ご先祖さまに対しても失礼にあたりません。最近では、一基でお供えする方も増えつつあります。
お墓用のお花は?
法要時にご本尊にお供えする花のほかに、お墓用のお花も用意します。墓前用の花は、両側にお供えしますので、花束 一対が基本です。
法事法要のお供え花の種類
お供え花を手配する際に、お花屋さんに「法要用」であることを伝えれば、基本的に問題ない花束かアレンジメントを作ってもらえます。
宗派などの決まり事が気になる場合には、寺院に確認すると安心です。
四十九日法要前までは、白を基調とすることが多いですが、四十九日法要以降はもう少し色合いを加えてもいいでしょう。また、故人の好きな花があれば、花束にいれてもらうといいでしょう。
最近は、仏花も「いかにも」感がなくなり、今時のキレイなものが増えましたね。
仏花にもよく使われる、桔梗やカーネーション、リンドウ等であれば、白い菊や百合と合わせても問題ありません。色味としては、淡いピンクや紫、青系、黄色などであれば大丈夫です。ただし、赤はお祝い事に使われる色なので避ける方が無難です。
また、以下のように、花の性質から避けた方が良いものもあります。
【お供えに避けた方がいい花じは?】
- 棘のある花(バラ、アザミ等)
- 香りが強い花
- 花粉が多い花
※ 百合など花粉が多いものは、花粉を取り除けば問題ありません。お花屋さんが対応してくれます。 - 毒を持つ花
この辺りは、注文時に「法要用」であることを、お花屋さんに伝えれば間違いありませんので、あまり細かく気にしなくても大丈夫です。
*****
以前、菩提寺のご住職の奥様とお話をする機会がありました。その際に、お供え花の大きさや、花の種類、花瓶などは実際どうなのか、細かく伺ったことがありました。奥様であれば、リアルなご意見を伺えるのではないかと思ったのです。。。
仏様のような柔らかな表情で、ひとこと。
「お花に合わせて活ければいいので、お気持ちで選んでくだされば結構ですよ」
考えてみればその通りですよね。自分で判断することが不安(面倒)なので、答えを知りたかっただけなんだと、気付かされました。お恥ずかしい限りです。。