仏壇にお供えするご飯は、毎日炊き立てのものと教えてられてきましたが、ライフスタイルの変化もあり、実際にはなかなかキビシイものがあります。
今回は、仏壇にお供えするご飯について、基本的な考え方をまとめてご紹介します。ご自身のライフスタイルに合わせてご判断ください。
仏壇にご飯をお供えする理由は?
仏壇へのお供え物にふさわしいものとして、五供(ごくう/ごく)があります。
【五供とは?】
- 香〜お線香
仏様が香りを召し上がるとされる解釈や、線香の香りは身を清らかにするともいわれています。 - 花(供花 くげ)
故人の魂の依り代であり、花のように心清くいてほしいという仏様の教えも表しています。 - 灯明・灯燭(とうしょく)〜ろうそく
ロウソクなどで明かりを灯すことで、暗い闇を照らし、煩悩(心をかき乱す欲)を捨て去り、明るい悟りに至るいう意味があります。 - 浄水(じょうすい)〜水やお茶
穢れがないことを意味する水をお供えします。 - 飲食(おんじき)
普段食べている炊きたてのご飯や果物などをお供えすることで、「日々おいしいご飯をいただいて満足に暮らせています」という感謝を表します。仏様はお供えしたご飯の香り(湯気)を召し上がります。
日々暮らせていることへ感謝の気持ちとして、ご飯をお供えするのです。そうであれば、「美味しいご飯」をお供えする理由も分かりますね。
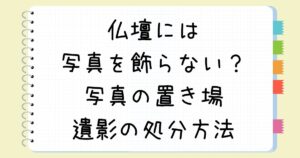
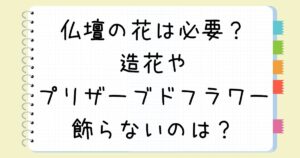
仏壇のお供えご飯に毎日炊き立てができないなら?
仏壇のお供えご飯は、毎日炊き立てのご飯がいいとされていますが、社会生活や食生活の変化もあり、毎日できないこともありますね。そんな場合の考え方です。
できれば朝の炊き立てご飯
感謝の気持ちとしてお供えするものですから、朝の炊き立てご飯はまず仏壇にお供えしてから食べるのが一般的です。
主食であるお米を食べることができる感謝を、仏様に報告する意味合いがあります。また、朝にお供えすることで、1日の家族の安全や健康を祈ることができるとされています。
朝のご飯である理由は、昔の僧侶は1日1食、午前中にしか食事を摂らなかったことによります。午前中に托鉢に回り、午前10時にその日の食事を摂りました。その食事も、自分に必要な分だけをいただき、残った分は、他の動物などに分け与えていたのです。
このことから、仏壇のお供えご飯も、朝の炊き立ての一番飯をお供えし、午前中のうちに下げるのです。
私の実家も、私が高校生くらいまではそうでした。その頃は、毎日お弁当だったので、学校がある日は母が毎朝ご飯を炊いていました。炊き立てのご飯は、最初に仏壇にお供えし、食事もお弁当作りもその後でした。
ご飯を炊いたときにお供えする
ライフスタイルの変化もあり、毎日ご飯を炊かなかったり、ご飯を炊くのは夜ご飯という家庭も珍しくありません。
そのような場合には、ご飯を炊いた際にだけお供えしても構わないとされています。
ご飯に限らず、果物やお菓子、お茶なども、新鮮なもの、淹れたてのもの、頂き物であれば頂いてすぐにお供えします。
これは、仏様はお供えしたご飯の香り(湯気)を召し上がるとされているからです。湯気のたたないものでも、新鮮なうち、新しいうちにお供えするのです。
保温・冷凍ご飯などを電子レンジで温めるのは?
時代や社会生活、食生活の変化もあり、毎日ご飯を炊かないことも、まとめてご飯を炊いて小分けに冷凍にすることも、珍しいことではありません。
炊いたときにだけお供えすればいいとされているくらいなのですから、冷凍ご飯を温めなおしたものをお供えしても、問題はないということなのでしょう。
ただ、冷凍ご飯や冷蔵庫などで冷えたご飯だと、上手に盛り付けられませんし、ご飯の湯気も立ちません。電子レンジなどで温め直してからお供えしましょう。
お供えにご飯以外は?
自分たちが食事をするタイミングでお供えをするという考え方もあります。
これには、日々の食事や生活への感謝の他に、仏様やご先祖様、故人と一緒に食事を楽しむ意味合いがあるとされています。
この考え方だと、自分たちの食事がパンや麺類であれば、同じものを小さなお皿などでお供えしても構わないことになりますが、これに関しては賛否両論あるようです。
宗派や菩提寺の考え方にもよりますので、一個人としてオススメできるものではありません。
どうしても気になる時、ご飯がないけど形だけ・見た目だけでも整えたい場合には、便利なイミテーションもあります。↓
【お供えのご飯はどうする?】
- 朝の炊き立てご飯をお供えするのがベスト
- ご飯を炊いたときにお供えするだけでもいい
- 冷凍ご飯などを電子レンジで温めてお供えしてもいい
- ご飯はなくても、淹れたてのお茶や、汲みたてのお水はお供えする
仏壇のご飯にラップをするのは?
ご飯をそのままお供えし、時間が経つとカピカピになります。乾燥予防や、虫除けなどの観点から、ラップをするのはどうかと考えてしまいますが、ラップは避ける方がいいでしょう。
上述の通り、仏様はお供えのご飯の香りや湯気を召し上がるとされています。ラップをしてしまうことで、香りも湯気も味わえなくなりますので、お供えの意味をなしません。
乾燥や、虫などの衛生面が気になる場合には、お供え後15分程度で下げれば済むことです。
仏壇のお供えを下げるタイミングは?
仏壇にお供えしたご飯は、15分程度で下げて構いません。むしろ、下げたご飯は「お下がり」としていただくものとされてきました。
上述の通り、仏様は、ご飯の香りや湯気を召し上がります。15分も経つと湯気も立たなくなりますので、下げて構わないのです。自分たちも食事をするのであれば、「お下がり」をいただく、あるいは自分たちの食事を片付ける時にお下げすればいいでしょう。
果物やお菓子などであれば、数日そのままお供えしておいても構いませんが、ご飯同様短時間でお下げしても構いません。
仏様には、「美味しいもの」をお供えするのが基本です。カピカピになったご飯や、食べ時が過ぎた果物、何日もお供えして埃が被ったお菓子では、むしろ失礼です。
美味しいものをお供えし、お下がりを美味しいうちに家族でいただく、と考えれば下げ時に悩むこともなくなるでしょう。
下げたお供えご飯はどうする?
お供えしたご飯は、本来は食事の際に食べるのが良いとされています。
ジャーなどに戻して、他のご飯と混ぜる
食事時であれば、お供えしたご飯を下げて、炊飯ジャーなどに戻し他のご飯と混ぜて一緒にいただくのが良いとされてきました。
ご飯を無駄にすることもありませんし、仏様からのお下がりを皆でいただくことになります。
冷凍しておく
食事のタイミングと合わない場合には、下げたお供えご飯をラップなどで包み、冷凍しておくこともできます。
お茶漬けや、おかゆ、チャーハンなどであれば、多少固くなっていても大丈夫です。
生ゴミとして捨てる
家に庭があれば、土の中に埋めることができます。他の生き物が食べることで、無駄になることなく次の命につながります。
庭がない、埋める場所や時間がないような場合には、生ゴミとして捨てましょう。お線香の香りや衛生面が気になる場合、下げた時にはすでに乾燥したような場合には、潔く捨てます。
ご飯を捨てる際にも、感謝の気持ちを持って手を合わせるとの考え方もあります。お供えご飯に限らず、食べられない食材や食べ残しなど処分するものに対しては、感謝の気持ちを持って処分するのが本来のあり方なのだと思います。
強制ではありませんし、そのまま捨てたところでバチが当たるわけではありませんが、無理のない範囲で丁寧に扱い捨てるといいでしょう。
*****
お供えとは、供養であり、感謝の気持ちの表れです。
社会生活や食生活の変化で、しきたり通りに毎日続けるのは困難なこともあります。信仰心にもよりますが、毎日できない、続けるのが大変、キツい、ツライ、っていうか無理、、というのであれば、形だけを追うのではなく、自分でできる範囲で対応する方がいいでしょう。
多忙な中、多様な情報が錯綜する現代では、「マナー」やあるべき論を正面から受け止めると、悩みや疑問を解決するどころか、自分の首をより絞めることもあります。そして、心を置き去りにしたまま、形だけを追いかけ、より生きづらさを感じてしまうものです。
無理のない範囲で続けられるよう、割り切って考えてみることもオススメします。
毎日当然のように、朝一で炊き立てご飯をお供えしていた私の母も、朝にご飯を炊かなくなると、お供えご飯も日課ではなくなりました。お茶やお水は、毎日交換していましたが、お供えご飯に関しては、さほど気にもしていないようでした。戦前生まれでも、そんなものですよ。










