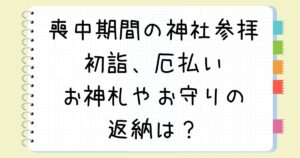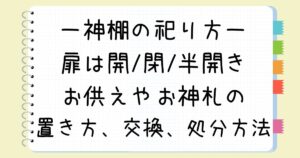葬儀の際に神棚を隠すと言いますが、誰が、どうやって、いつまで隠すのか、葬儀の際の神棚封じについてまとめておきます。
葬儀の際に神棚を隠す?
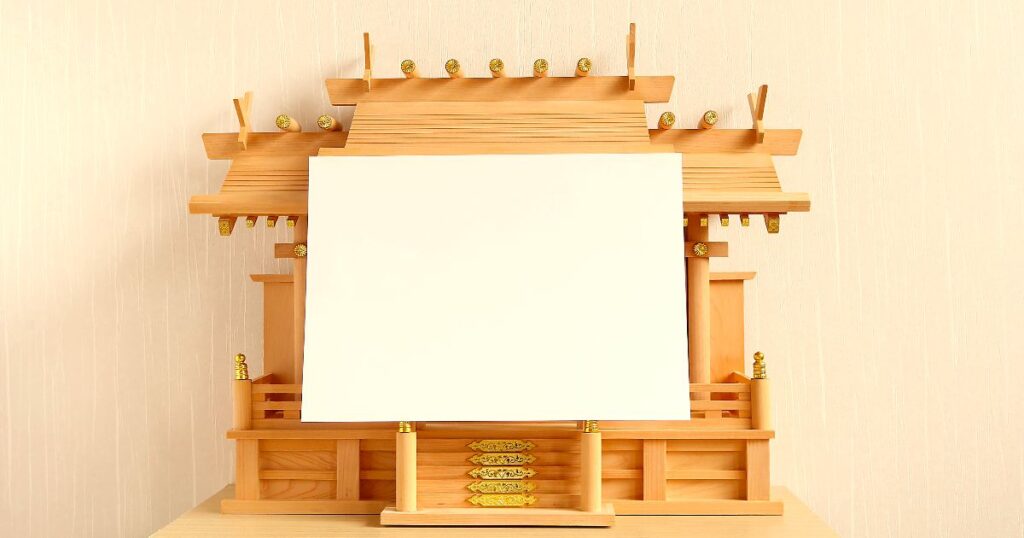
家族に不幸があった際に、家の中の神棚を半紙で隠すことを「神棚封じ」と言います。
葬儀の際に「神棚封じ」をする理由は?
神道では、死は穢れとされます。
そのため、忌明け(50日)までは、神の領域へ穢れが入らないように半紙で「神棚封じ」をします。忌中は、神社への参拝や、家の神棚へのお供えや参拝も避けるなど、神様に近づいてはならないとされています。
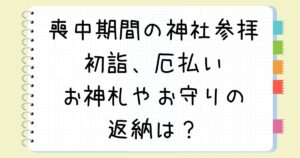
死は穢れの本当の意味は?
神道では、「死」はもっとも重大な「穢れ(けがれ)」であるとされています。
この「穢れ」という言葉が難しいのですが、汚れている、キタナイという意味ではありません。神道での「穢れ」とは、「気枯れ(けがれ)」を意味します。亡くなった人がケガレているのではなく、「死」そのものがケガレ・気枯れなのです。
【気枯れ/穢れとは?】
人は死んでしまうことで、自分で生きる力がなくなり、神様からいただいた「気」が「枯れ」た状態になること
身内の人も、大切な人の死に接することで、自身も悲しみ、元気がなくなり、「気」が「枯れ」、正常(清浄)ではない状態のこと
不浄もまた、キタナイという意味ではありません。
【不浄とは?】
エネルギーにあふれた正常(清浄)でない状態のこと
「死」は肉体的にも精神的にも正常(清浄)ではなく不浄であり、「気枯れ」によって精神的にも肉体的にも生命力が衰えたり消滅します。だから、神道では「死は穢れ」と考えるのです。
気の枯れた状態である遺族は、神様と距離を置きます。十分な時間(50日)をかけ、自分の状態が正常(清浄)に戻ってからお参りするために、神棚封じを行うのです。
神棚封じは誰が行うの?
神棚封じは遺族ではなく、第三者が行うべきものとされてきました。
神棚は、神への畏敬の念を持ってお祀りするものです。
家族が亡くなり、精神的にも肉体的にも生命力が衰え、気枯れである遺族は、神へ近づいてはならないとされています。そのため、神棚封じをするのは、遺族ではなく第三者とされたのです。
自宅で葬儀を営む場合には、葬儀屋さんが神棚封じを行ってくれることが多いですが、近年は、社会生活の変化もあり、家族(遺族)が行うことも多いようです。
神棚封じの手順は?
神棚封じの手順そのものは、とてもシンプルです。
【神棚封じの手順は?】
- 神棚の神様にご挨拶をし、誰が亡くなったかを報告します
- 神棚の御神酒や米や塩などのお供え物や、榊などをすべて下げます
- 神棚の扉をきちんと閉め、正面を隠すように白い半紙などを貼ります
- しめ縄がある場合は、しめ縄の上から半紙などを貼ります
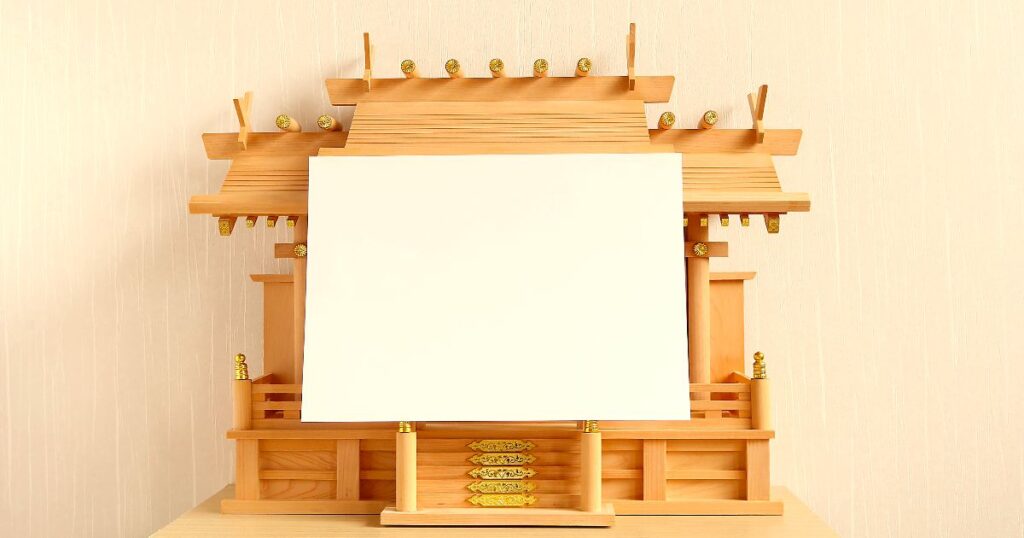
半紙などを貼る際は、神棚を傷つけないよう気をつけましょう。セロテープなど、糊が残りにくく、扱いやすいテープで貼るといいでしょう。
神棚を隠す際の半紙や代用品は?
神棚封じを行う際には、書道で使う半紙が一般的です。小学校の書道などでも使う一般的なサイズ(333mm×243mm)で構いません。
半紙がない場合には、コピー用紙など、白い紙で代用することもできます。B4用紙のサイズが364mm×257mm。半紙よりも少し大きくなります。
神棚のサイズは家庭により様々ですが、正面を隠すことができれば十分ですので、神棚全体が隠れる必要はありません。
上述の手順でも説明しましたが、次の点には注意しましょう。
神棚を隠す期間や、その期間中の注意点は?
神棚を隠す期間は?
神棚封じの期間は、神道での忌中期間である50日とされています。
仏教では49日で忌明けですが、神棚は神道です。神道では、50日間が忌中の期間、五十日祭を持って忌明けとされます。
【仏教徒なら?】
仏教や他の宗教を信仰していても、神棚は神道の考え方に則るのが作法です。神道での忌中期間は、神棚封じを行います。
神棚を隠した半紙は誰が撤去するの?
神棚封じの半紙を撤去するのは、忌明け後になるのですから、家族(遺族)で構いません。
仏式の場合、葬儀社が中陰祭壇を片付ける際に神棚の半紙も撤去してくれる場合もあります。
神棚封じの撤去の手順は?
忌明け後に、神棚封じの半紙を撤去する手順も、シンプルです。
【神棚封じを撤去する手順は?】
- 塩で身を清めます
- 通常通りの拝礼をします(二拝二拍手一拝 が一般的です)
- 半紙を取ります
- 普段と同様、御神酒や米や塩などのお供え物や、榊を祀ります
半紙が忌中に剥がれたら?
セロテープなどで貼っているだけですから、忌中期間に半紙が剥がれてしまうこともあります。その場合には、張り直すだけで構いません。
本来であれば、遺族とは関係のない第三者が張り直すのが望ましいのですが、遺族が張り直しても構わないとされています。遺族が張り直す場合には、塩で身を清めてから行いましょう。
忌中の拝礼やお供えは?
家族を失い、体力も気力も失せ「気が枯れている」状態であるから、神棚封じを行い、神様と距離を置いているのです。日常的な拝礼やお供えも同様に、忌中期間は控えます。
【お供えしないのは失礼?】
忌中期間は、御神酒や米や塩などのお供え物や、榊を祀ることを控えても、失礼には当たりません。むしろ、忌中期間に神棚に触れることの方が神様に対して失礼であると、神道では考えますので、気をつけましょう。
神棚封じ期間中にお正月が来たら?
お正月でも、忌中期間は神棚封じをしたままにします。同様に、初詣などの神社の参拝も控えます。
初詣は忌明け後、神棚封じを解いた後に行います。
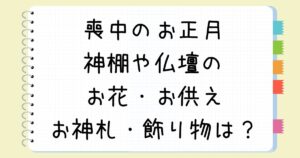
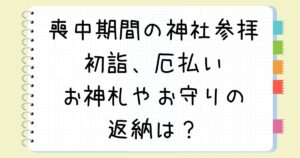
仏教徒でも神棚封じは行うべき?
仏教や他の宗教を信仰している場合でも、神棚は神道の考え方に則り、忌中期間は神棚封じを行います。
ただし、仏壇を閉じる必要はありません。仏教では、死は穢れとは考えませんし、むしろ御本尊にお参りする方が良いとされています。
また、神式の仏壇である祖霊社は封印する必要はありません。
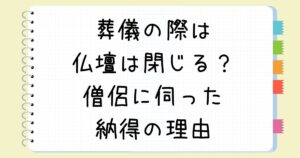
神棚封じは、地域慣習や神社によっても、作法や考え方が異なります。わからない場合には、お札を頂いた神社に確認するか、葬儀社に相談してみるといいでしょう。
弔事では、地域慣習や家の考え方に加え、迷信などを気にする方もいらっしゃいます。親族にそのような方がいる場合には、不要なトラブルや不快な思い、心乱されることがないよう、穏便に進めるのが無難です。