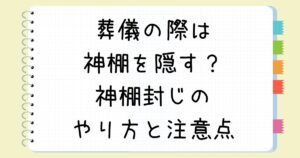家族が亡くなると、葬儀の前に仏壇の扉は閉めるとも、開けたままとも聞きます。葬儀の際の仏壇について閉じるかどうか等、曹洞宗の僧侶に直接伺ったことも含めて記しておきます。
葬儀の間は仏壇を閉じるはホント?
葬儀屋のサイトなどを見てみると、葬儀〜四十九日までは仏壇の扉は閉めるとの解説が圧倒的に多いようです。
神棚と一緒に仏壇も閉じる?
家族が亡くなり、故人が自宅に帰ってくる場合、葬儀屋さんに遺体の搬送をお任せすることが多いです。
葬儀屋さんは、遺体を寝かせ、必要な処置や旅立ちの準備を施し、葬儀の準備をしてくれます。その際に、神棚がある家であれば、半紙で「神棚封じ」をします。仏壇があれば、「四十九日(忌中)は仏壇の扉を閉じてください」と遺族にお願いすることが多いようです。
宗派にも寄りますが、仏教本来の考え方から言えば、仏壇の扉を閉じる必要はなく、「開けたままにする」が正しいとされています。
宗派による考え方の違いは?
宗派によって、「開けておくのが基本」の宗派と、「開ける」「閉める」で意見が分かれる宗派とあるようです。
葬儀でも仏壇は開けておくのが基本の宗派は?
浄土真宗、浄土宗、日蓮宗などは、葬儀でも仏壇は開けておくものと考えられています。
これは、拝む対象がご本尊であること、葬儀も法要もご本尊の前で営まれること、ご本尊の導きによって成仏することなどが理由です。
葬儀で仏壇は開ける・閉めるの意見が分かれる宗派は?
真言宗、曹洞宗、臨済宗などでは、葬儀の際に仏壇を開けるか閉めるかで意見が分かれます。
「宗派」と言っても、日本における伝統的な仏教には、「十三宗五十六派」があります。浄土真宗、日蓮宗、曹洞宗、臨済宗など教えの中心となる宗旨(しゅうし)が13宗、さらに教義・信仰対象などの違いや歴史的経緯から56の分派があるのです。
同じ○○宗でも「派」が異なれば考え方も異なります。さらに地域慣習が優先されることもあるので、意見が分かれてしまうのです。そのため、仏教の考え方では「開ける」ものであっても、あえて「閉じる」とする理由が様々あるのです。
【仏壇を閉じる理由は?】
- 葬儀の際に、ご本尊にお尻をむけてしまうことがある
- 葬儀の準備などで慌ただしく、仏壇の前を横切るなどの失礼がある
- 葬儀では故人対して読経し冥福を祈る
- 神道の教えとの混同や、地域慣習や迷信に倣う
ミニチュア菩提寺である仏壇に祀られているご本尊へ失礼がないようにと、神道の教えとの混同によるとの、2つの考え方があるようです。積極的に「閉じる」理由がないことだけは明確ですね。
仏壇を閉じるは勘違い?
ご本尊への失礼がないようにというのはわかりますが、神道の教えとの混同は厄介ですね。
神道では、死は穢れ(気枯れ)とされています。そのため、神の領域へ穢れが入らないように、忌明け(50日)までは半紙で「神棚封じ」をします。忌中は、神社への参拝や、神棚へのお供え・参拝も避けるなど、神様に近づいてはならないとされています。
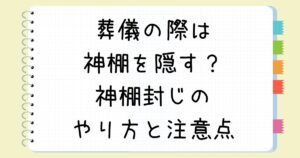
仏教では死は穢れではありませんが、神道の考え方が混同し、「仏壇を閉じる」ようになったと考えられます。
他にも、「お清めの塩」も、神道の教えとの混同です。仏教では、死は穢れではないのですから、清めるという考え方がありません。
合わせて、「友引に葬儀をしない」のは、ただの迷信です。

仏壇の扉に半紙は必要?
そもそもで、仏壇を閉じる明確な理由はありません。また、半紙は神道での「神棚封じ」、結界を張るためのものです。
いずれにしても、神道の考え方ですから、仏壇に半紙は不要です。
仏壇の扉はいつまで閉じておく?
上述の通り、そもそもで仏壇を閉じる必要はありません。
葬儀屋さんが仏壇を閉じたり、地域慣習などで閉じた場合でも、葬儀終了後は仏壇を開けて構いません。
ただ、菩提寺に閉めておくよう言われたり、地域慣習や、家の考え方でそうしてきたのであれば、開ける時期も含めて、従う方が賢明です。
葬儀中の仏壇に関して曹洞宗の僧侶に伺った納得の理由
曹洞宗の僧侶とお話をする機会があり、仏壇の扉についても伺ったことがあります。
その寺院では、「こちら(僧侶の寺院)では」との前置きがありましたが、「仏壇の扉は開けたままにしておきます、と檀家さんにお話ししています」とのことでした。その理由を、次のように説明していただきました。
【仏壇を開けたままにする理由】
大切なことは、ご本尊やご先祖様に手を合わせること
仏壇には、御本尊が安置されています。先祖の位牌もあります。
※ 浄土真宗等の宗派によっては位牌はありません
ご本尊やご先祖様への感謝は葬儀でも、忌中でも変わるものではありません。特に、ご本尊や先祖は故人を極楽浄土へと導いてくれる存在ですから、遺族は故人が成仏できるよう祈ることが大切なのです。
ですから、葬儀の間も通常通りに、水やお花、仏飯をお供えします。
その後、四十九日までは中陰祭壇を設けて位牌や遺骨、遺影を中央に、その他香炉、線香立て、生花、盛り菓子等を置くのですが、仏壇と中陰祭壇のお供えは一方だけでなく両方に行うようにします。
仏壇の扉を閉じるかどうかについては、宗派としての考え方というよりも、その地域的な風習や家に伝わる民間風習と合わさったのではないか。どちらが絶対に正しいというのでなく、地域によって、家によって異なる可能性もあるので、分からない場合は菩提寺や親戚、地域の見解に従うのが良いでしょう、とのことでした。
実際に悩んだ場合には、菩提寺に確認するのが最善の解決策ですね。