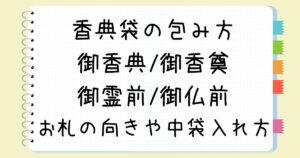仏式の葬式(お通夜、葬儀、告別式)に包む香典の表書きは、多くの宗派では同じですが浄土真宗では異なります。
最近は、宗派などをあまり気にされない方も多いように思われますが、知っておけば、失礼になることはないので安心です。今回は、浄土真宗のお葬式(お通夜、葬儀)での知っておきたいことや注意点をまとめておきます。
浄土真宗の葬式(お通夜、葬儀)香典や供物の表書きは?
香典や供物の表書きは「御霊前」「御仏前」?
仏教の葬式(お通夜、葬儀、告別式)では、香典の表書きを「御霊前」にするのが一般的です。
浄土真宗の場合は、「御仏前」または旧字体である「御佛前」を使います。これは、亡くなるとすぐに極楽浄土へ行き仏になる、「往生即身仏(おうじょうそくしんぶつ)」とされているからです。お通夜、葬儀の際にはすでに仏様なのですから、供えるものは「御仏前」なのです。
水引は、一般的な弔事で使用するもので問題はありません。「黒白」「双銀」「藍銀」、地方によっては「黄白」。「繰り返すことがないように」の意味を込めた「結び切り」か、「末長く付き合う」意味を込めた「あわじ結び」を使います。
【仏教での一般的は考え方は?】
仏教の多くの宗派では、亡くなってから四十九日までは霊の状態にあるとされています。そのため、お葬式(お通夜、葬儀、告別式)の香典や供物・供花も「御霊前」。四十九日法要以降が「御仏前」です。
表書きに「御香奠」「御香典」は?
仏式では、「御香典」「御香奠(ごこうでん)」が、いつでも使える表書きです。
香の代わりに供えるお金という意味であり、葬儀から法要まで使えるのです。水引は、黒白か双銀の結び切りやあわじ結び。
香典は、あくまで哀悼の意を伝えるもの、要は「気持ち」ですから、宗派として表書きが間違えていたところで、相手に不快な思いをさせたり、後ろ指さされるようなことではありません。時代も変わりつつありますし、さほど神経質にならなくてもいいのだと思いますが、宗教や宗派で違いがあることを知っていると、安心ではありますね。
浄土真宗にはNGワードがある?
葬式(通夜・葬儀・皇別式)での一般的な忌み言葉は?
浄土真宗に限らず、葬儀の場ではいくつかNGワード・忌み言葉があります。
【弔事に相応しくない言葉】
- 「重ね重ね」「度々」のような重ね言葉
- 「再び」「続いて」のような不幸が続くことを思わせる言葉
- 「消える」、数字の四(死ぬ)や九(苦しむ)のような不吉な言葉
浄土真宗では使わない言葉は?
浄土真宗では、上述の一般的な忌み言葉の他に、宗派の思想として使わない言葉があります。
【浄土真宗では使わないお悔やみの言葉例】
- ご冥福をお祈りします
- 安らかにお眠りください
- 他界、旅立ち、天国、草葉の陰
浄土真宗の「往生即身仏」人は亡くなると直ぐに成仏するとの教えからです。
そのため、次のようなお悔やみの言葉をかけるのがいいでしょう。
【浄土真宗でのお悔やみの言葉】
- 〇〇様を偲びお念仏申し上げます
- 浄土よりお導きください
- 謹んで哀悼の意を表します (弔電用)
「冥福」「冥途(めいど)」 「冥福を祈る」とは、迷うことなくあの世への旅路(冥途)を終え、故人が無事に成仏することを祈る言葉です。浄土真宗では、すでに成仏しているのですから、不要な祈りというか、そもそも考え方が違うのです。
また、仏さまは、ゆっくりやすんでいるのではなく、真実の世界へと導くために休むことなくはたらかれていると、考えられています。眠っているわけではありませんので、こちらも使いません。
「他界」しないのは、「往生」浄土に往って生まれるからなのです。
キリスト教の神の世界である「天国」でも、墓場の下やあの世である「草葉の陰」でもなく、仏さまは極楽浄土にいらっしゃいます。
浄土真宗では、「供養」という概念もありません。四十九日法要なども、「魂が成仏するように」という意味での供養ではなく、故人や先祖を通じて自分達が仏法に接して功徳を積むという目的で営まれます。
浄土真宗には戒名はない?
浄土真宗には、戒名がありません。仏法を拠り所として生きていくことをを決意した仏弟子であることの証である「法名(ほうみょう)」をいただきます。
俗世間を生きた人が仏門に入り、仏教における戒律を厳守し仏道修行するために授けられる誡(いまし)めの名「戒名」とは、異なります。
浄土真宗での葬儀の位置付け
同じ仏教とはいえ、浄土真宗ならではの教えがあるので、宗派が異なるとなかなかに難しいものがありますね。
浄土真宗本願寺派では、「葬儀」を次のように説明しています。
【葬儀とは?】
「生」に執らわれ、死の現実から目を逸らせがちな私たちに、(亡き人も含めて)一つのけじめとして死を受けいれさせ、一歩前に進む契機を与えるのが葬儀です。
浄土真宗では、「すべてのものを必ずお浄土へ生まれさせ仏に成らせる」という誓いがあります。往生し仏さまになっているのですから、慰めや別れの儀式(告別式)は不要であり、むしろ仏さまとなられた徳を讃嘆すると考えます。
ですから、葬儀とは、亡き人の死を受け入れ、普遍的な価値を持って関わり続ける存在、敬うべき存在として、残された人たちが受け止めていく儀式にあたるのです。
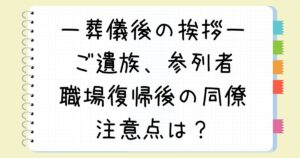
浄土真宗の葬儀で焼香その他マナーの注意点は
浄土真宗の葬儀では、お焼香にも注意が必要です。
【浄土真宗での焼香の流れ】
- 焼香台の前に立ち、ご本尊に軽く一礼します
- お香をつまみ、そのまま香炉に入れます
※焼香の回数は派によって異なります - 念珠を両手にかけて合掌し、「南無阿弥陀仏」と念仏を唱え拝みます
- ご本尊に一礼をして下がります
お焼香では、派によって回数は異なりますが、お香を額にいただかずに、そのまま香炉にいれるのが、浄土真宗の作法です。
わからない場合には、ご遺族の方のやり方を真似るに限ります。前の人のやり方をまねるとよいとよく言いますが、真後ろにいると直前の人の作法はよく見えませんし、人それぞれ違う違うことはよくあります。。
仏前に香を供えることを供香といいますが、お焼香はその一つです。お焼香は、阿弥陀如来さま(仏さま)への敬いの心であり、仏様をお参りする自分自身を清めるものでもあります。香りが隅々まで平等に行き渡るところから、すべての人にわけへだてなく行き渡る仏さまの慈悲に例えられます。
浄土真宗には「清め塩」がない?
死を穢れ(気枯れ)とみなすのは、神道の考え方です。
会葬御礼などに清め塩が入っていることも多いため、お葬式の後に清め塩を振りかけないことに、抵抗を感じる方も少なくないことと思います。仏式では、死は穢れとは考えませんので、浄土真宗に限らず「清め塩」は不要です。
浄土真宗では、死を通して、生老病死の現実に向き合い、仏さまの教えを仰ぎ、生きる意味を見つめるのが葬儀とも考えられています。さらに、迷信的なものはきっぱり否定します。
*****
一口に仏教といっても宗派によって教えも考え方も異なります。参列するお葬式(通夜・葬儀・告別式)の宗派ごとに、その教えを学び理解するのは、現実的にはかなり難しいですね。私は、お葬式に参列する度に、宗派の作法を確認するようにしていますが、鶏並みなのか終わると忘れてしまうようです。。