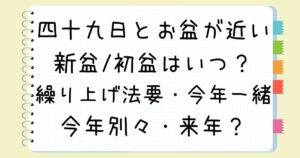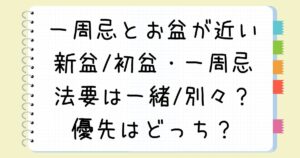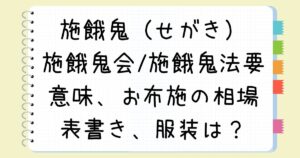浄土真宗では新盆/初盆をしないと聞きますが、本当に何もしなくていいのものか、仏壇のお供えや提灯飾りはどうすればいいのか、お盆の法要でのお布施の相場はどのくらいなのか、浄土真宗の新盆/初盆に関する基本的な考え方をまとめておきます。
門徒の方だけでなく、浄土真宗の親族や親しい人が亡くなられた場合にも、参考にしていただければ幸いです。
浄土真宗は新盆/初盆をしないの?
新盆/初盆とは?
新盆(にいぼん・しんぼん・あらぼん)は、家族が亡くなって初めて迎えるお盆 のことです。初盆(はつぼん・ういぼん)と言う地域もあります。
お盆には、いつもはあの世にいるご先祖様の霊が家へ戻るので、丁寧におもてなしし先祖供養をする風習があります。
亡くなって初めてのお盆(新盆/初盆)では、故人が迷わず家に戻ることができるようにと、特別な提灯や灯籠を飾るのが一般的です。

浄土真宗では新盆・初盆はしないの?
浄土真宗では初盆や毎年のお盆という考え方がありません。
同じ仏教でありながら、考え方が異なるのは、浄土真宗の教えによるものです。
【浄土真宗の教え】
浄土真宗では、往生即成仏(おうじょうそくじょうぶつ)、即身成仏(そくしんじょうぶつ)との教えがあります。亡くなると、阿弥陀如来に導かれすぐに成仏するとの教えです
既に成仏している、つまり煩悩や束縛からも完全に離れ、仏様として真に安らかな境地に至っているわけですから、追善供養をするという考え方がありません。
【他の宗派の考え方は?】
他の宗派では、亡くなると7日ごとに審判を受け四十九日の審判で極楽浄土へ行けるかが決まります。
故人の生前の行いで審判が下されるのですが、故人の極楽浄土行きを祈る遺族(現世の人)が法要という善を行う(追善供養)ことで、故人によい裁きがくだるよう後押しします。その後も、極楽浄土にたどり着くまで、一周忌、三回忌などの追善供養(追善法要)が続きます。
三十三回忌で長い修行が終わり、故人は菩薩(ぼさつ)の道に入ります。
あわせて、既に仏様になっているのですから、この世に故人の霊が留まるという考え方も、家にお迎えする故人の霊もないのですから、いわゆる新盆・初盆がない、そもそもでお盆という考え方がないのです。
【お盆は宗教行事?】
お盆とは、日本古来の祖霊信仰と仏教が融合した行事であり、風習です。
浄土真宗では、年忌法要もない?
浄土真宗でも、一周忌・三回忌・七回忌・十三回忌・十七回忌・二十三回忌・三十三回忌を営みます。一般的には、三十三回忌を弔い上げとしますが、決まりではありません。
ただ、他の宗派とは意味合いが異なります。
浄土真宗の年忌法要は、故人の冥福を願う追善供養ではなく、親族や家族で集まって故人を偲び感謝するために営まれます。また、法要の機会に、御仏の教えに触れることを目的としています。
浄土真宗の初盆で仏壇のお供えや提灯飾りは?
実際には、浄土真宗の寺院や門徒(他の宗派では檀家)でも新盆法要(初盆法要)やお盆法要は営まれますが、それは歓喜会(かんぎえ)にあたります。
浄土真宗のお盆は歓喜会
浄土真宗でも、新盆・初盆には親戚や故人と縁のあった方が集まります。
故人の霊の初めての里帰りをもてなし供養するためではなく、故人に感謝し、故人を偲びつつ、仏様の教えに触れる大切な機会、歓喜会(かんぎえ) なのです。
前述の通り、浄土真宗では亡くなると即仏様に生まれ変わる往生即成仏(おうじょうそくじょうぶつ)、即身成仏(そくしんじょうぶつ)との教えがあります。そのため、故人の極楽浄土を祈る追善供養がありません。
一方で、浄土真宗には、「生きている私達自身が仏法を聞く」ことが功徳であり阿弥陀如来さまに救われるという教えがあります。
つまり、僧侶に読経していただくのは、先祖供養ではなく現世に生きる者たちのためです。仏様の教えに触れ、念仏を唱え火を灯し、香や花をお供えし、この機会を与えてくれた先人に感謝するのです。
一般的なお盆と浄土真宗のお盆(歓喜会)では、主に次の点で異なります。
【浄土真宗のお盆(歓喜会)でやることは?】
- 切子灯籠(切籠灯篭、盆灯篭)を一対仏壇の前に下げる
- 打敷(うちしき / 法要等の際に使う三角形の布)を仏壇にかける
- 供笥(くげ)に白い丸餅(お華束、おけそく)を重ね盛りする
【浄土真宗のお盆(歓喜会)ではやらないことは?】
- 迎え火 や 送り火 を焚かない
- 盆提灯や白提灯は飾らない
- 新盆における提灯や精霊棚などは不要

切子灯篭(切籠灯籠、盆灯篭)とは?
切子灯篭とは、浄土真宗でお盆時期に飾る吊り灯籠です。切籠灯籠、盆灯篭とも呼ばれ、悪霊を払う力があると言われています。
本来吊るす物ですが、住宅事情などもあり、近年は自立型(スタンド式)のものもあります。
打敷(うちしき)とは
打敷(うちしき)とは、仏壇を装飾する布製の敷物、荘厳具(しょうごんぐ)です。浄土真宗では主に、逆三角形のものを使用します。
お盆には白・金・青色のいずれかを使用します。夏用と冬用がある場合には、初盆では夏用を使いましょう。
サイズや色も選べます↓
供笥とは?
お華束(おけそく)をのせる台を供笥(くげ)と言います。似たようなもので「高台」がありますが、こちらは略式なので、用意するなら供笥にしましょう。
供笥の大きさはいくつかありますが、丸餅をのせることを考えると2寸5分くらいがちょうど良いでしょう。
この他、仏壇へのお供えは、大谷派(お東)は御華束(丸餅)のみを、本願寺派(お西)は御華束(丸餅)以外に菓子や果物なども必要です。

浄土真宗では、提灯や盆飾りをしないのが一般的ですが、地域や家によっては地域の特産物などで飾り付けをすることもあります。近い親戚(浄土真宗の門徒)や、菩提寺、葬儀社などに確認してみましょう。
仏事に関しては、宗派の他に、寺院の考え方や、地域差もあります。社会生活の変化や住宅事情もありますので、それぞれ無理のない範囲で用意することが大切です。
浄土真宗の初盆で御布施の金額は?お車代や御膳料は?
浄土真宗の初盆で御布施の相場は?
浄土真宗の初盆法要におけるお布施の額は、寺院によっても異なりますが目安としては以下の通りです。
【浄土真宗の新盆でのお布施相場は?】
- お布施:3万円程度
- 御車代、御膳料 など
初盆法要やお盆法要は、寺院か家で執り行います。
新盆の場合には、参列者が多いことから寺院で営むことも多いようですが、家側の事情、地域性、寺院の規模や門徒数等でも異なります。
御布施の金額も寺院によって異なります。お布施は安ければいい(包む側としては負担が少ないのは助かりますが、、)、高ければいいというものでもありませんので、寺院に「どの程度お包みすればいいのか」と確認すると間違いありません。
自宅で行う場合のお車代は?
自宅に来ていただく場合には、お布施とは別にお車代をお包みします。家側で僧侶を送迎したり、タクシーを手配した場合には、不要です。
車でお越しいただく際には、駐車スペースの確保し、事前にお伝えしておきましょう。
僧侶の送迎は、早いタイミングだと僧侶の予定が定まっていないこともあります。法要(歓喜会)が近くなってから、送迎やお車代を確認した方が良さそうです。
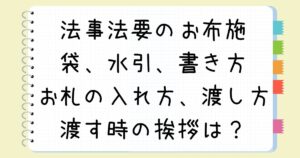
新盆で御膳料や御斎は必要?
お盆の時期は、僧侶も門徒をまわっているため、滞在時間は長くても30分程度が一般的です。
そのため、会食などに僧侶が参加されることはあまりなく、お茶を出す程度で構わないとされています。その場合でも、御膳料はお渡しします。
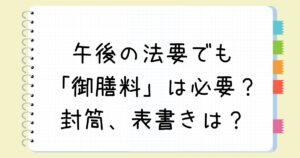
お盆の時期は、僧侶も寺院での法要や門徒まわりがあり、かなり多忙です。新盆の法要(歓喜会)をする場合には、早めに相談し、日程調整をするのがオススメです。
新盆に限らずですが、短時間とはいえ僧侶が家にお越しになる際には、トイレもきれいに掃除しておきましょう。
*****
浄土真宗の場合は新盆・初盆をしないとは言いますが、盆飾りをしないだけで、法要を営むことは珍しくありません。ただ、盆飾りの内容も異なりますし、新盆・初盆の考え方がそもそもで異なります。
先祖への感謝、自分の功徳を積むためのものであり、お供え物もご先祖さまではなく「ご本尊である阿弥陀如来さま」にお供えします。実際のやり方は地域性もあるため、浄土真宗の年長者や、寺院や葬儀社に聞くのが間違いありません。
なお、親族や年長者といっても聞く相手を間違える(宗派が違うなど)と、厄介なことになりますので、くれぐれもご注意ください。