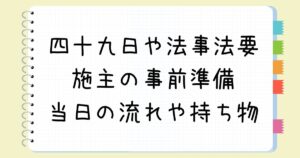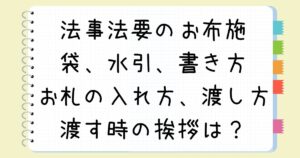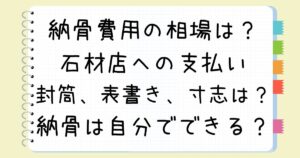法事の際に悩むことの1つに卒塔婆供養があります。
卒塔婆(そとば、そうとば)は、お墓の後や横に立てかけてある、長くて細い板のことです。誰が、何のために、どのように用意し、処分するのかなど、卒塔婆供養に関して、仏事を行う際に知っておきたい基礎知識をまとめておきます。
卒塔婆供養とは?
卒塔婆とは?

卒塔婆は、先祖供養や故人供養の際に立てられる細長い板ですが、古代インドにおける「仏塔」が起源とされています。
仏塔はお釈迦様の遺骨を納めた塔のことです。これをサンスクリット語で「ストゥーパ (stûpa) 」と言い、それに漢字を当てはめて「卒塔婆」となったと言われています。
仏教では寺院や塔を建てることで功徳を積むことができる、とされていますが、お金持ちでなければ塔を建てることは無理ですよね。そこで、塔の代わりに卒塔婆を建てるようになったのです。
卒塔婆には、塔を建てるのと同じ功徳があるとされています。
卒塔婆供養とは?
浄土真宗以外の宗派では、納骨法要や年忌法要の際に、施主や列席者がお墓の周りに卒塔婆を立てる風習があります。
仏教では、卒塔婆を立てることは善とされています。
卒塔婆を立てることは善を積むことであり、故人の冥福につながると考えられるため、法要の際に立てるのです。そのため、卒塔婆を立てることを卒塔婆供養といいます。
卒塔婆の文字は何?
卒塔婆には、次のような文字が墨で書かれています。宗派により若干異なります。
【卒塔婆の文字は?】
- 梵字「キャ・カ・ラ・バ・ア」
・「キャ」:「空」、宝珠形
・「カ」:「風」、半円形
・「ラ」:「火」、三角形
・「バ」:「水」、円形
・「ア」:「地」、四角形 - 供養する故人の戒名
- 起塔の理由(「○回忌」「盂蘭盆会」「彼岸会」など)
- 起塔年月日
- 施主名
梵字は、人体や宇宙を構成する五大元素を意味します。
卒塔婆に書いてある故人が成仏できるようにという願いが込められるとともに、卒塔婆を立てた人の功徳に繋がるとされています。
この梵字の意味する5つの形は、元々はお釈迦様の遺骨を納めた五重塔の形でした。現在の木製の卒塔婆の形にも反映されているのです。
卒塔婆の立て方、頼み方、価格は?
卒塔婆は誰でも立てることができるし、本数の決まりもありません。法要の施主だけでなく、他の法要列席者が何本お願いしても構いません。
卒塔婆は誰が立てるの?
卒塔婆には、誰が何本立てるなどの決まりがありません。
故人お一人に対して卒塔婆を1本立てることが一般的ですが、地域や寺院、家の慣習によっても異なります。
「沢山の卒塔婆を立てる方が供養になる」と考え、法要列席の全家庭が1本ずつ立てる家もあれば、「施主が1本卒塔婆を立てるだけで良い」という考え方もあります。
地域や家の慣習、考え方も異なりますので、施主側から卒塔婆を建てるか確認するのは、控えた方がいいかもしれませんね。半ば矯正されているように受け止める方もいるかもしれませんし。。
卒塔婆の頼み方は?
卒塔婆を立てるとは、卒塔婆供養をお願いすることですので、事前に寺院に依頼し、卒塔婆を用意してもらいます。寺院側に所定の申込書があることが多いです。
寺院の法要であれば寺院に直接申し込みますが、年忌法要のように特定の故人の法要の場合には、施主から寺院にまとめて依頼するのが一般的です。
寺院側で文字を書き入れるため、2週間程度前には寺院に依頼しましょう。
法要参列者がお願いしたい場合には、その前までに施主に申し入れる必要があります。法要への参列の返信をするタイミングなどで、話をするのがオススメです。
卒塔婆の価格は?
卒塔婆の価格は、寺院ごとに決まっています。1本につき2千円~1万円程度というお寺が多いようです。
寺院によって多少の幅がありますが、家や法要ごとに異なるお布施とは異なりますので、寺院に問い合わせればすぐにわかります。
法要参列者もお願いしたい場合には、施主に確認する方がいいでしょう。
卒塔婆料の渡し方や袋は?
卒塔婆料を渡す封筒は?
施主がお寺に卒塔婆料を渡す場合は、白無地封筒を使います。封筒の表書きは「卒塔婆料(卒塔婆代、塔婆料など)」、下に氏名を書きます。
書き方、お札の向きなどは、お布施の包み方と同様です。↓

施主以外の方も卒塔婆を立てる場合には、寺院ではなく施主に渡し、施主からまとめて寺院にお支払いします。
卒塔婆を依頼した方は、法要前に施主に卒塔婆代を渡すのが基本ですが、離れている場合などには法要の際に渡してもいいでしょう。その場合でも、香典用の不祝儀袋ではなく、白無地封筒に「卒塔婆料」などの表書きと、その下に氏名を記入します。
卒塔婆料の渡し方は?
法要前や法要を終えた後、お礼のご挨拶をし、お布施を渡す際に一緒に渡して構いません。法要前に、ご挨拶を兼ねて寺院に持参することもあります。
特に決まりはありませんので、慌ただしくならないタイミングでお渡しするといいでしょう。地域や家の慣習、寺院の考え方によっても異なりますので、わからない場合には、寺院に相談するのが間違いありません。
卒塔婆を処分するタイミングや方法は?
卒塔婆は木で作られたものなので、古くなると黒ずんだり、傷んで腐ってきたりもします。処分する時期や期間等に決まりはありませんが、古くなってきたら菩提寺や霊園等の管理事務所に依頼して処分してもらいます。
卒塔婆はいつ処分する?
故人の最初の卒塔婆供養は、納骨供養の時に営まれます。以降は、年忌法要に限らず、お盆やお彼岸、祥月命日など、お墓をお参りする際に卒塔婆供養を営むことができます。
そのため、1年程度で新しい卒塔婆と交換し、古いものを処分するという考え方があります。
一方で、新しい卒塔婆は古い卒塔婆の隣に立て、痛んだり朽ちてきた時や、卒塔婆がいっぱいになってきた時、新たに納骨法要がある時などに処分するという考え方もあります。
決まりがあるわけではありませんので、立てる卒塔婆の本数などに応じて対応するといいでしょう。
墓地や霊園によっては、古くなった卒塔婆を管理事務所側で処分することもあります。この場合には、利用規約などに書いてあったり、契約時に管理事務所から説明があるかと思います。
卒塔婆の処分方法は?
卒塔婆を処分方法は、寺院や霊園によって異なりますので、確認しましょう。
【卒塔婆の処分方法は?】
- 墓地や霊園等の管理事務所に依頼して、処分してもらう
- 墓地や霊園等の管理事務所が、(依頼しなくても)適切に処分する
- 墓地や霊園内のお焚き上げ場や指定の場所に置いておく
など、処分方法が異なります。寺院や霊園によっては、「お焚き上げ料」を別途収める必要があります。
*****
卒塔婆料は、法事でかかる費用の中では珍しく単価設定されているものです。誰が何本立てるかなどは、地域や家の慣習、寺院の考え方によっても異なります。
わからない場合には、年配者や菩提寺の僧侶に確認すると間違いありません。当日に慌ただしくならないよう、法要の打ち合わせ時など、早めに相談しておくことをオススメします。