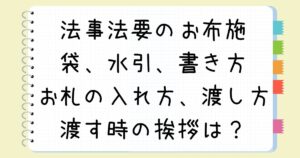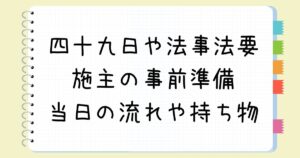家族が亡くなると数年毎に法要を営みますが、丸1年後の場合は一周忌、一回忌どちらの言い方が正しいのか、周忌と回忌はどう使い分けるのか、年数計算に迷った時の数え方、お布施の相場などをまとめておきます。
周忌と回忌の意味と違い
周忌と回忌には「周」と「回」という「まわる」を意味する漢字が使われています。
両方とも「まわる」という意味は共通しているのですが、使い方は次の点で違います。
【回忌と周忌の違いは?】
- 回忌:数え年と同じ数え方、亡くなった年を「1」とカウント
- 周忌:満年齢と同じ数え方、亡くなってから丸1年経過すると「1」とカウント
法要は一周忌と一回忌どっちが正解?
言葉としては、一回忌も一周忌も正しいものですが、亡くなった翌年の法要という意味では、一周忌が正しい呼び方です。
一回忌とは?
一回忌とは、亡くなった日(命日)にあたります。
一回忌法要は?
一回忌の法要は、亡くなって最初に執り行われるお葬式にあたります。
一周忌とは?
一周忌とは、亡くなった日から丸1年経過した日(命日)にあたります。
一周忌法要とは? 二回忌法要はないの?
もう大丈夫ですね。一周忌の法要は、亡くなった翌年の命日に執り行う法要のことです。
亡くなって1年間は、いわゆる「喪中」です。故人を偲び慎んだ生活を営む風習があります。その期間が終わるので、二回忌は特別に一周忌と呼ぶようです。

法要の数え方はどっち?
一周忌が終わると、また「回忌」で数え年のカウントします。ややこしいですね。。
一周忌以降の年忌法要は、三十三回忌までは一の位が3と7と交互に行われ、その後は五十回忌、百回忌となります。
【年忌法要はいつ?】
- 三回忌:丸2年
- 七回忌:丸6年
- 十三回忌:丸12年
- 十七回忌:丸16年
- 二十三回忌:丸22年
- 二十七回忌:丸26年
- 三十三回忌:丸32年
- 五十回忌:丸49年
百回忌までありますが、十七回忌、三十三回忌、五十回忌で弔い上げとすることが多かったようです。これも家や地方の風習、宗派や菩提寺との関係によって異なります。
最近では七回忌や十三回忌で弔い上げをするなど、短くなる傾向にあります。
【弔い上げとは?】
弔い上げとは、年忌法要を締めくくるための最後の儀式です。
弔い上げによって、決められた年の命日に執り行われてきた法事(法要)は終わります。その後は、故人のみの法要ではなく、他の先祖ともに供養することになります。
少子化や社会生活の変化で、頻繁に法事法要をすることも難しくなってきたこと、回忌を重ねるごとに故人を知っている人が少なくなること、施主や参加者の経済的負担など、さまざま理由があります。
基本的に、法事や法要はやらなければならないものでも、やらないとバチがあたるものでもありません。
早めに弔い上げをすることもあれば、弔い上げ自体せずに故人ごとの法事や法要を終わらせることもあります。大切なのは、故人に対する思いです。いつまで続けるかは、家族や親族とも相談し、折り合いをつけ判断するようになりますね。
回忌の簡単な数え方は?
法事における回忌計算方法は、数え年の考え方と同じです。「西暦に年忌の数を足して1引く」 方法で求めることができます。
(例)2022年に亡くなった故人の13回忌 :2022+13-1=2034年
数え年の考え方は年忌法要だけではなく、初七日から四十九日までの日数計算も同じで、亡くなった日を「一日目」と数えます。地方によっては、死亡前日から数えるところもあります。
一周忌やその後の回忌法要のお布施の相場は?
お布施の相場は、菩提寺の考え方、菩提寺と家の関係性、地域慣習などによっても異なります。相場はありますが、参考程度とされるのがいいでしょう。
同日に複数の法要を営む場合には、基本的にはお布施は別モノと考え、それぞれ分を足したものを一つの封筒に包みます。ただ、これも菩提寺の考え方によって「一式〜」となることもあります。いずれにしても、菩提寺に確認するしかありません。
| 法要 | お布施相場 |
|---|---|
| 葬式 (お通夜、葬儀/告別式 一式) | 20〜100万円 ※ 戒名料にもよる |
| 四十九日法要 | 3〜10万円 |
| 納骨法要 | 1〜5万円 |
| 新盆/初盆法要 | 1〜5万円 |
| 一周忌法要 | 3〜10万円 |
| 回忌法要(年忌法要) 3回忌以降 | 1〜5万円 |
| その他の供養 | 1万円〜 |
この他に、お車代や御膳料を別途お包みします。これは、1日(1回)あたりですので、複数の法要を営んでも、同日であればそれぞれ5千〜1万円程度です。
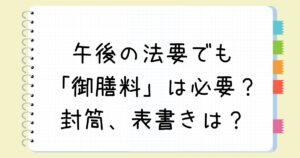
お布施の封筒は基本は白封筒、水引なしです。

お布施の袋や、渡し方などは、下記の記事にて詳しくまとめています。↓