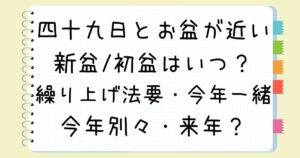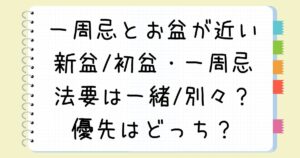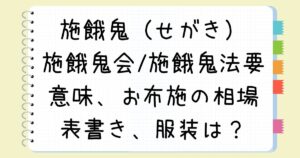家族が亡くなって初めて迎えるお盆が新盆・初盆です。
頻繁にあることではないので、通常のお盆と何か違いがあるのかと悩んだり、必要な飾りを誰が用意するのか分からず戸惑ったり、、、不安や疑問だらけですよね。
新盆を迎える場合に知っておきたい、通常のお盆との違いや飾りなどの基本的な考え方をまとめておきます。
新盆・初盆とは?読み方は?
新盆・初盆とは?
亡くなって四十九日の忌明け後初めてのお盆のことを、新盆・初盆と言います。地域によって呼び方が異なりますが、意味することは同じです。
四十九日前にお盆が訪れる場合は、初盆を翌年に行うのが一般的です。
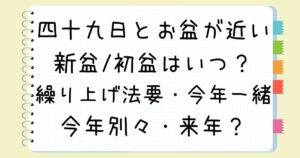
新盆・初盆の読み方は?
新盆・新盆は、地域によって読み方も異なります。
【新盆・初盆の読み方は?】
- 新盆:にいぼん・しんぼん・あらぼん
- 初盆:はつぼん・ういぼん
社会生活の変化もあり、地域差といってもかなりマチマチなのが現実かと思います。気になる時は親族や地域の年長者、寺院に聞いてみるのが一番です。
通常のお盆との違い
お盆とは、ご先祖様の霊をご自宅にお迎えし、ご先祖様や故人を偲び供養する日本独自の風習のことです。
新盆/初盆も、故人をお迎えして供養するという点では同じですが、初めて自宅に帰ってこられるため、昔から丁寧に供養する風習があります。
お盆と新盆/初盆でやることの違いはあるの?
例年のお盆よりも、丁寧に華やかにお迎えする風習があります。
【新盆/初盆ならではのことは?】
- 白提灯を用意する
- 新盆(初盆)法要を行い、法要後に会食(御斎)する
新盆/初盆用の白提灯の飾り方は?
お盆の時期には、ご先祖様が迷わず里帰りできるよう、道しるべとして提灯を灯すのが一般的ですが、新盆/初盆では、初めて戻られる故人のために白提灯を別に用意する風習があります。

新盆/初盆に白提灯を飾る理由
この白提灯は、新盆/初盆でのみ使います。
盆提灯では華やかな絵柄が入っているものが多いのですが、白提灯は白木で作られた白紋天(しろもんてん)と呼ばれる白無地の提灯です。これには清浄無垢の白で故人の霊を迎えるという意味があります。
新盆/初盆の白提灯の飾り方〜いつから、どこに、いくつ飾る?
白提灯はいくつ飾る?
白提灯は、初めてお盆を迎える故人用に1つあればいいとされています。
白提灯は誰が用意する?
白提灯は1つあればよいので、故人の家族が購入することが多いです。
故人の兄弟姉妹や親戚、故人と親しかった方が、新盆/初盆に合わせて盆提灯を贈る風習もあります。
最近は住宅事情などの変化もあり盆提灯用にということで現金を送るケースや、仏壇用のお供えを用意するケースが増えつつあるようです。
白提灯や盆提灯はいつから飾る?
白提灯も盆提灯と同様に、故人の霊が迷わずに家に帰ってこられるよう道しるべとして灯すものです。故人の霊を迎える「迎え火」、故人の霊を送る「送り火」としての役割があります。
そのため、お盆の初日である迎え盆(7月または8月13日)から最終日である送り盆(7月または8月16日)まで飾るのが一般的です。火を灯すのも、期間中の夜が中心となりますが、特に決まりがあるわけではありません。
昔はろうそくだったので、不在時や就寝時は消したり、そもそも火をつけず飾るだけだったりしたようです。最近はろうそく型の電池やLEDライトが主流ですので、好きな時間帯につけたり消したり、1日中付けていたり、それぞれです。
白提灯や盆提灯には、故人を偲び敬う気持ちの表れでもあります。お盆期間前後にも飾ることに問題はありません。お盆の月の初め頃(7月上旬か8月上旬)から飾る家庭もあります。
白提灯や盆提灯はどこに飾る?
新盆/初盆の白提灯は、故人の霊が迷わずに初めての里帰りができるよう、目標として玄関先や軒先に吊るして飾るのが一般的でした。
住宅事情もあるため、玄関先や軒先が難しい場合には、窓辺や仏壇の前、ベランダなどでも問題はありません。もとはろうそくでしたが、最近はLEDライトが主流、コードレスもあります。
時代とともに白提灯も変化していますね。
絵柄のある盆提灯は、盆棚や精霊棚(しょうりょうだな)、仏壇の両脇に飾ります。
お盆が過ぎたら白提灯はどうする?使い回ししていいもの?
初盆/初盆の白提灯は故人ひとりにつき1つが原則で使い回しはしません。つまり、1回限りです。
お盆が終わったら、新盆/初盆用の白提灯は燃やして処分します。
昔は送り火として燃やしたり、自宅の庭でお焚き上げしたり、菩提寺に持っていきお焚き上げしてもらったり、地域によっては川に流したりするのが一般的でした。
住宅事情の変化もあり、送り火も自宅の庭でのお焚き上げも難しくなりました。 火事予防や環境への配慮からお焚き上げを受け付けていない寺院もあります。
お焚き上げが難しい場合には、自宅で塩で清めてから新聞紙などに包んで燃えるゴミとして処分しましょう。
【盆提灯は?】
通常の盆提灯は毎年使うことができます。お盆の後は、ほこりなどを掃除して翌年まで大切に保管しましょう。
初盆/初盆に提灯を贈る際の注意点
新盆/初盆を迎える家へ贈るお供物として、過去には盆提灯が最高のものと考えられていました。贈られた盆提灯の数が多ければ多いほど、故人が慕われていた証との考え方もあったそうです。
そのため、親族だけでなく、故人と親しかった方から贈られることもあります。
盆提灯を贈る場合には、贈る側の気持ちだけでなく遺族への配慮が必要です。
【盆提灯を贈る前に】
- 盆提灯を贈る前に、できればご遺族に確認しましょう
※ 贈られた側のスペースの問題もあります - 家族以外が提灯を贈る場合には、絵柄入りの盆提灯にしましょう
- お盆の月の初め頃(7月上旬か8月上旬)に届くように手配しましょう
- 一対で贈るのが正式ですが、1つだけで贈ることも失礼ではありません
※ 贈られた側のスペースの問題にも配慮しましょう - 掛け紙(のし紙)をかける場合には「御仏前」が一般的です
社会生活や住宅事情の変化もあり、盆提灯の代わりに金品を包むことも増えています。
【現金を包む場合には?】
盆提灯を贈る代わりに金品を贈る場合には、不祝儀袋を利用し、表書きは「御提灯料」や「新盆献灯料」。故人との関係にもよりますが、3千円から1万円ほどとされています。
新盆/初盆法要は?
通常のお盆の場合は、法要を行わない地域や家も増えているとはいえ、新盆/初盆は初めてのお盆なので通常のお盆よりも丁重に供養します。
お盆の初日は迎え火、最終日には送り火がありますから、7月か8月14日の盆中日を目安に初盆(新盆)法要を執り行うことが多いです
「新盆/初盆法要」を営み、法要後に集まった方々(親戚や故人と縁のあった方など)と会食を行なう形が一般的ですが、社会生活の変化もあり、家族だけで行うケースが増えているようです。菩提寺や親族と早めに相談するといいでしょう。
法要を執り行う場合には、お布施、お車料、御前料を用意します。
お布施は、菩提寺との関係や宗派によっても異なりますが30,000円~50,000円前後、お車料や御前料はそれぞれ5,000〜10,000円が一般的です。
参列者への返礼品(引き物/引出物)も用意します。
- 返礼品(引き物/引出物)の表書きは「志」や「粗供養」「新盆(初盆)供養」などと記載した掛け紙(のし紙)を使う
- 水引は黒と白の結び切りが一般的(地域によって異なります)
- 名入れは施主のフルネームか「〇〇家」など
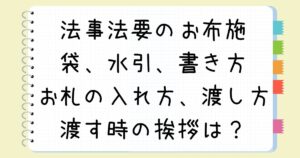
新盆は、故人の霊が初めて自宅に戻られるため通常のお盆よりも手厚く法要する風習があります。
宗派や菩提寺の考え方にもよりますし、決まり事もありません。社会生活の変化に加え、近年の社会的要因でかなり簡略化されたこともあり、家によっては過去には戻らず時代にあわせた法要へと変化していくものと思われます。
そもそも、故人の霊は家族に会うために家へ戻るのですから、家族が元気で過ごしていることと、無理ない供養の方法が望ましいといえるでしょう。
風習や形式にとらわれ過ぎず、故人を偲ぶ気持ちを何よりも大切にし、穏やかな時をお過ごしくださいね。