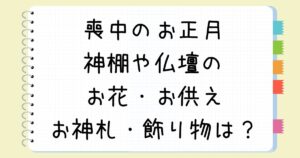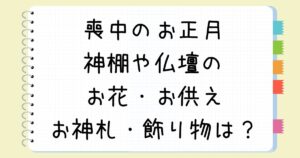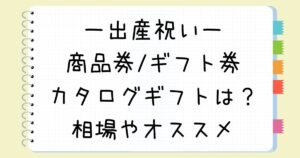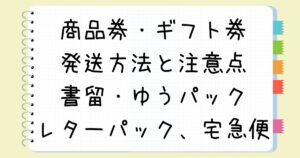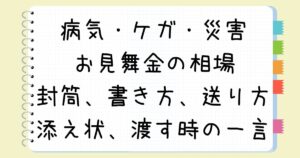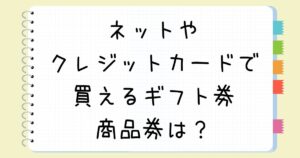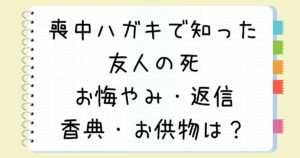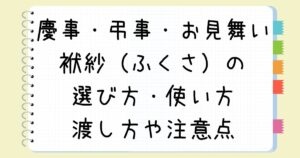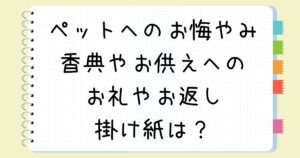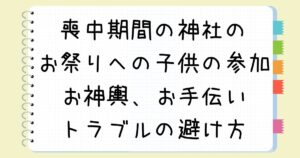喪中期間の年末の挨拶に関してまとめておきます。
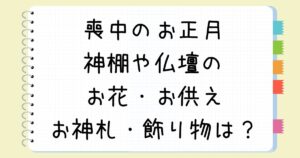
喪中の年末挨拶に「良いお年を」は大丈夫?
年末の「良いお年を」とか「良いお年をお迎えください」の挨拶は、自分が喪中、相手が喪中いずれでの場合でも大丈夫です。
「良い」という言葉を使いますが、これ自体がお祝いの言葉ではないからです。
実際に、喪中はがきのテンプレートなどでも「皆様にはよいお年をお迎え下さいますようお祈りいたします」などは、よくあります。
もちろん、自分が喪中でも、相手が喪中でも、「あけましておめでとうございます」の新年の祝賀は慎みます。
喪中に「年越しそば」は食べていいの?
年末行事のひとつでもある「年越しそば」。これは、年越し蕎麦(そば)の意味を考えると、問題ないことがわかります。
【年越しそばの意味とは?】
- 蕎麦のように、細く長く元気で暮らせることを願う
- お金が集まることを願う
:金銀細工師が蕎麦粉団子で金粉を集めたため - そばが切れやすいことから、旧年の厄災を切ることを願う
つまり、縁起やゲン担ぎであり、慶事ではありませんので、問題はありません。

個人的には、「ずっとおそばに」のげん担ぎが好みです
喪中の忘年会や新年会の参加はどうする?
12月〜1月には、忘年会や新年会は、忌中(仏式で49日)であれば、お断りした方がいいでしょうが、喪中であれば本人の気持ちの問題でしょう。
【喪中期間の考え方は?】
- 配偶者、親:12〜13ヶ月
- 子ども:12〜13ヶ月
- 兄弟・姉妹・祖父母:3ヶ月〜6ヶ月
お正月は1年間控えますが、一般的な喪中期間は上述の通りです。これも、家や地域によってもことなりますし、故人との関係性や本人の悲しみの深さによっても異なります。
自分が喪中であれば、まだ気持ちの整理がつかない場合には、欠席して問題はないでしょう。
相手が喪中の場合には、声がけ程度で留め、無理に参加を誘うようなことが控えましょう。会社の行事や、取引先とのお付き合いなど、社会的な事情もありますので、声をかけることに問題はないでしょう。
特に、忘年会の場合には、「今年一年お疲れ様」「今年もお世話になりました」の意味合いがあるので、自分が喪中であれ、相手が喪中であれ、あまり深く気にする必要はないかもしれません。
一方、新年会の場合には、「おめでとう」から入りますので、喪中の人の気持ち次第と言えるでしょう。ただ、ビジネスではプライベートと切り離し、忌引き明けは通常モードに入る方も珍しくありません。