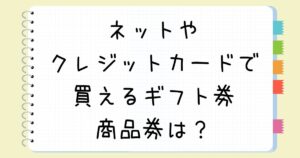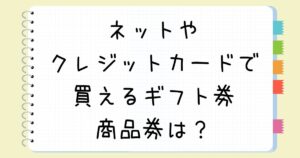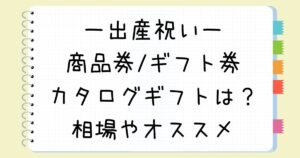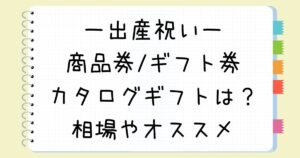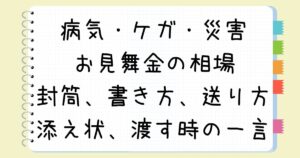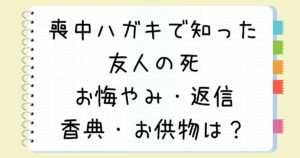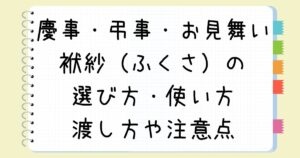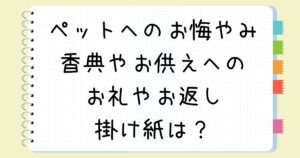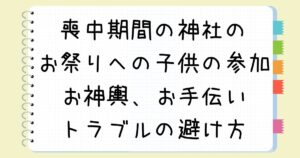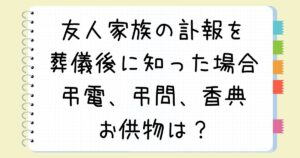お祝いやお礼などで商品券やギフトカードを贈る機会がありますが、送る方法や品名などの書き方、注意点などをまとめておきます。
金券・商品券・ギフトカードを送る方法は?
金券・商品券・ギフトカードを安全に送ることができるのは、書留(簡易書留・一般書留)かゆうパックです。補償なしでよければ、レターパックプラスがオススメ。
【金券・商品券・ギフト券の発送方法】
- 補償不要:レターパックプラス
- 5万円までの補償:簡易書留
- 5万円以上の補償:一般書留
- 品物等と一緒に送る:ゆうパック
コスパ最強はレターパックプラス
レターパックには2種類あります。

| 料金 | 投函方法 | 集荷 | 配達方法 | サイズ | 重量 | 厚さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レターパックプラス | 520円 | 郵便ポスト投函 可能 厚さ3cmを超える場合は 郵便局窓口 | ◯ | 手渡し 受領印または署名 | 340×248mm A4ファイルサイズ | 4kg以内 | 封筒の封ができれば 制限なし |
| レターパックライト | 370円 | 郵便ポスト投函 可能 | × | 郵便受け投函 | 340×248mm A4ファイルサイズ | 4kg以内 | 3cm以内 |
使うなら、レターパックプラス一択です。
【レターパックプラスが凄すぎる理由】
- 郵便局窓口のほかに、ローソン、100円ローソン、ミニストップなどのコンビニで購入可能
- 20枚セットなら郵便局オンラインショップでも購入可能
- 厚さ3cm以内であれば、郵便ポストに投函可能
- 集荷可能
- 全国一律520円
- 追跡可能
- 配達時手渡しなので誤配や行方不明の可能性ほぼなし
- 紛失時などの補償なし
- 現金を送ることはできません
紛失時などの補償なしとはいえ、手渡し・追跡可能ですから、誤配などの可能性もほとんどありません。
郵便物のように配達はしたけど、相手は受け取ってないと言う、、という厄介ゴトともほぼ無縁です。
贈るものが、10万、20万と高額であれば、補償があるほうがいいでしょうが、それ以下の場合には個人の判断です。

私は、なにかと多用しています
総務省郵便課によると、「レターパックは信書でも信書以外でも送れるし、商品券は現金ではないので送ることは可能」とのこと。
書留は?
書留には3種類ありますが、商品券やギフト券の発送で使えるのは、一般書留か簡易書留です。
金券や商品券が5万円までであれば簡易書留、それ以上であれば一般書留で送ります。
【一般書留とは?】
- 基本料金+480円(損害要償額10万円まで)
- さらに5万円ごとに+23円、上限500万円
- 引き受けから配達までの送達過程を記録
- 郵便物の破損や紛失時に実損額を賠償、上限500万円
【簡易書留とは?】
- 基本料金+350円(損害要償額5万円まで)
- 引き受けと配達のみ記録
- 郵便物の破損や紛失時に実損額を賠償
商品券などの有価証券の書留での発送方法です。
【一般書留/簡易書留の発送方法】
- 市販の封筒などに宛先、差出人の郵便番号、住所、氏名を記入します
- 1 の封筒などに金券・商品券などと、必要であれば添え状(手紙)などを入れます
- 郵便局の窓口で一般書留か簡易書留を指定し、規定の料金を支払います
料金は、普通郵便料金(定型郵便物の場合 重さ25g以内84円、50g以内94円)と簡易書留料金350円〜/一般書留料金480円〜の合計額
【現金書留とは?】
- 現金封筒(現金書留専用封筒)1枚 21円 を使う
- 基本料金+480円(損害要償額1万円まで)
- さらに5,000円ごとに+11円、上限50万円
- 引き受けから配達までの送達過程を記録
- 郵便物の破損や紛失時に実損額を賠償、上限50万円
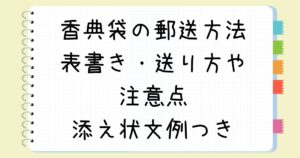
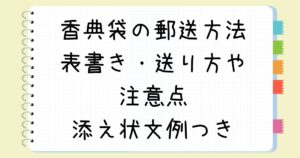
宅急便・宅配便は?
ヤマト運輸の宅急便や、佐川急便などの宅配便では、金券・商品券などの有価証券を送ることは法律で認められていません。
有価証券の範囲は広く、現金や小切手、手形、株券、証券だけでなく商品券やプリペイドカード等も含まれます。
ゆうパックは?
ゆうパックでは、金券・商品券などの有価証券を送ることができます。
- 集荷可能
- ローソンなどから発送可能
- 引き受けから配達までの送達過程を記録
- 破損や紛失時に実損額の賠償(上限30万円)
- セキュリティサービス(+420円)追加の場合には上限50万円
民間企業の宅配便では有価証券を送ることはできませんが、元は国営の郵政公社ですから、特別です。ただし、現金を送ることはできません。
普通郵便は?
商品券やギフト券は普通郵便で送ることも可能ですが、補償も追跡もありませんし、配達時も郵便受け投函です。
500円程度のギフトカードなどであればいいでしょうが、額面によってはオススメしません。
ゆうパックやレターパックで送る場合の品名欄の書き方は?
ゆうパックやレターパックで送る場合には、品名を描く必要があります。
レターパックの場合には、破損や紛失時の補償がありませんので、「商品券」「ギフトカード」などでも構いませんが、事故予防のためには「書類」あたりが無難です。



私は、いつも「書類」です。
ゆうパックの場合には、品名欄に商品券の種類や額面を記入しておくと、紛失時などの補償手続きが楽になります。「商品券」のみだと、領収書などの提示により証明する必要があります。
ただ、受け取る側のことを考慮すると、品名に「JCBギフトカード1000円券10枚」など記入されているのは、気分はよくありませんね。品物などと一緒に送るとき以外は、金額的にも補償的にも使い勝手はよくありませんので、ゆうパックは金券等の郵送方法としてはイマイチといえるでしょう。
【金券・商品券・ギフト券の発送方法】
- 補償不要:レターパックプラス
- 5万円までの補償:簡易書留
- 5万円以上の補償:一般書留
- 品物等と一緒に送る:ゆうパック
【商品券は楽天で!!】
楽天で商品券やギフト券を購入すれば、オンラインショップから直送してもらえるので、簡単で間違いありません。