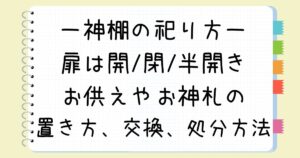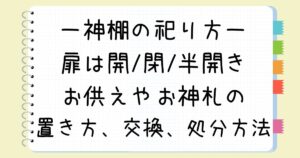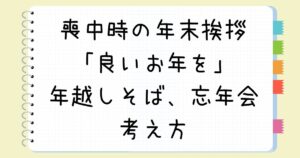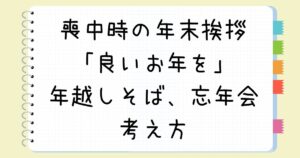服喪期間の初詣や厄払い・安産祈願・七五三・合格祈願などの祈祷、お札や守りの扱いなどの考え方をまとめておきます。
喪中期間は神社にお詣りするのはダメ?
結論になりますが、神社へのお詣りを控えるべき期間は、喪中期間ではなく神道での忌中期間、一般的には50日間です。
喪中期間の神社参拝はいけないとするブログ記事も散見されますが、全て勘違い。遠慮すべきは、「喪中」ではなく「忌中」期間です。
【神社参拝に関するよくある勘違い】
- 喪中の1年間は神社に行ってはいけない
- 服喪中は、鳥居をくぐってはいけない
- 服喪中は、賽銭するのもいけない
- 服喪中は、厄払いや七五三、お宮参り、安産祈願、合格祈願もいけない
なお、「服喪中でも鳥居をくぐらず、脇道や裏道から入れば問題なし」というのは、ただの屁理屈です。忌中期間は脇道や裏道でも神社には入りませんし、忌が明ければ堂々と鳥居をくぐり参拝して構いません。
忌中と喪中の違いは?
上述のような勘違いが生じるのは、「喪中(もちゅう)」と「忌中(きちゅう)」の区別がついていないからでしょう。
仏教、神道いずれでも、喪中の範囲は2親等以内(配偶者、祖父母、親、兄弟姉妹、子、孫、それぞれの配偶者)で考えるのが一般的ですが、家や故人との関係性によっても異なります。
神道における忌中とは?
神道では、不幸があってから50日間を忌中とするのが一般です。
人が亡くなると、50日間は御霊として存在しているとされています。死後50日後に行われる五十日祭(ごじゅうにちさい)で、故人は家庭を守る祖先神(そせんしん)になると考えられています。
また、遺族は、近親者が亡くなることで、肉体的にも精神的にも生命力が衰え消耗します。その期間は、外部との接触を控え、身を慎み、静かに祈ることで故人の御霊を清めるとされているのです。
この50日間は、神社への参拝を控え、家にある神棚も「神棚封じ」を行うことで、神様との接触を控えます。
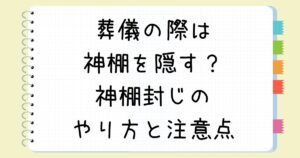
仏教における忌中とは?
仏教では、忌中は49日間です。四十九日法要が区切りとなり、忌明けになります。
仏教では、故人は7日ごとに生前の行いについて裁きを受け、7回目(49日目)の最後の裁判で極楽浄土へ行けるかの判断がくだされます。この期間は、まだ霊として彷徨っているため、故人が成仏するよう生きている遺族が追善供養を営みます。
遺族や近親者による追善供養の助けもあり、故人は極楽浄土へ旅立つこととなり、忌明けとなります。
喪中とは?
仏教でも、神道でも、喪中期間(服喪期間)は1年と考えるのが一般的です。
遺族が、身内を失った悲しみを乗り越え、通常の生活に戻るために必要な期間とされています。
過去には、服喪期間には喪服を着て、静かに過ごしたものですが、時代も社会生活も変わりました。多くの人は、お葬式(葬儀・告別式)が終われば、喪服を脱ぎますし、1週間もすれば仕事や学校にも戻り、日常生活に戻ります。
ただ、結婚式などの慶事への参加は、故人との関係性にもよりますが3〜6ヶ月程度控えます。お正月だけは、現在でも1年間は控えるのが通例です。これは、仏教でも神道でも、同様です。
「死は穢れ」の本当の意味は?
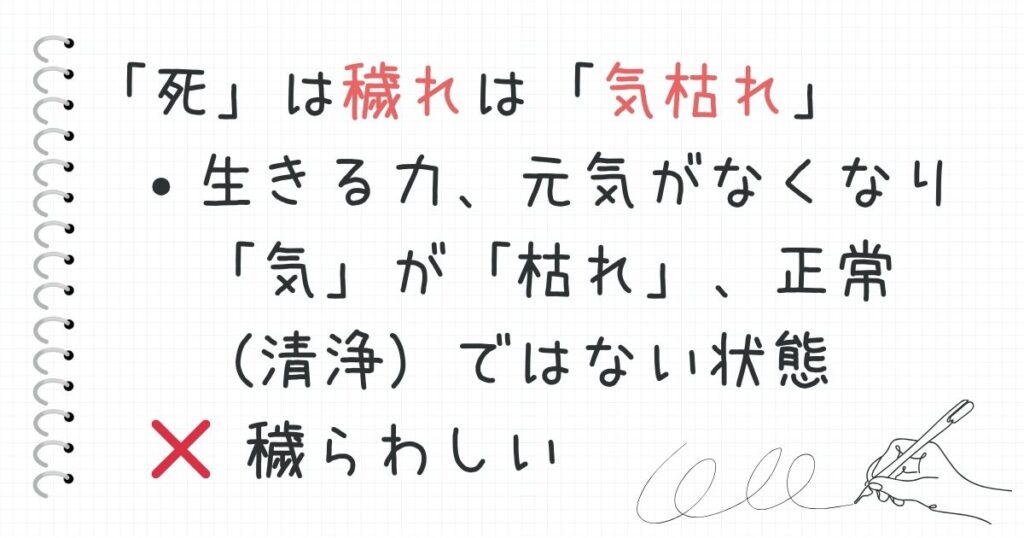
神道では、「死」はもっとも重大な「穢れ(けがれ)」であるとされています。
この「穢れ」という言葉が難しいのですが、汚れている、キタナイという意味ではありません。神道での「穢れ」とは、「気枯れ(けがれ)」を意味します。亡くなった人がケガレているのではなく、「死」そのものがケガレ・気枯れなのです。
【気枯れ/穢れとは?】
人は死んでしまうことで、自分で生きる力がなくなり、神様からいただいた「気」が「枯れ」た状態になること
身内の人も、大切な人の死に接することで、自身も悲しみ、元気がなくなり、「気」が「枯れ」、正常(清浄)ではない状態のこと
不浄もまた、キタナイという意味ではありません。
【不浄とは?】
エネルギーにあふれた正常(清浄)でない状態のこと
「死」は肉体的にも精神的にも正常(清浄)ではなく不浄であり、「気枯れ」によって精神的にも肉体的にも生命力が衰えたり消滅します。だから、神道では「死は穢れ」と考えるのです。
その穢れ/気枯れの状態で、神様の前に出ることを避けるために、忌中期間は神社への参拝を遠慮するのです。
喪中・忌中期間の初詣は?
忌中、忌明け後の喪中期間の違いが分かれば、初詣の考え方もわかりますね。
忌中期間の初詣は?
忌中期間は、神社への参拝は控えるとされている期間です。初詣でも、神社への参拝は控えるものと考えましょう。
初詣は、松の内(1月7日か15日)にお詣りするのが一般的ですが、その期間を過ぎると神様が不機嫌になるわけではありません。忌明け後、落ち着いてからゆっくりお詣りに行きましょう。
忌明け後、喪中期間の初詣は?
忌明け後であれば、神社への参拝は基本的には問題ありませんが、神道でも1年間は服喪期間であり、お正月のお祝いは控えます。
ただ、神道において控えるべき事項ではありませんので、故人が亡くなった時期や、ご自身の気持ち次第とも言えるでしょう。
忌中でも初詣に行きたい場合には?
忌中でも、初詣に行きたい場合には、寺院にお詣りしましょう。
神道とは異なり、仏教では死は穢れではありませんし、忌中であっても参拝に問題はありません。
なお、初詣の人気スポットには、寺院もあります。
【初詣で人気の寺院は?】
- 成田山:成田山新勝寺、真言宗智山派
- 川崎大師:金剛山金乗院平間寺、真言宗智山派
- 浅草寺:金龍山淺草寺、聖観音宗(天台宗系単立)
初詣で人気の寺院でなく、菩提寺へご挨拶にお詣りするのもいいものです。
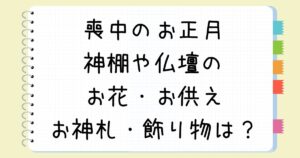
喪中・忌中期間の安産祈願・合格祈願や祈祷は?
上述の通り、忌中期間は神社への参拝は控えるのですから、祈願や祈祷のために参拝するのも控えるものと考えます。
ただ、神社本庁によると、「忌中(五十日祭まで)は神社参拝を遠慮しますが、やむを得ない場合はお祓いを受けるのが良い」とされてはいますので、忌明けを待たずに祈願や祈祷でお詣りしたい場合には、お祓いを受けてお詣りするといいでしょう。
事前に、お詣りする神社へ連絡を入れておきましょう。
なお、忌明け後の喪中期間での祈願や祈祷には問題はありません。
喪中・忌中期間の厄除け・厄払いは?
忌中期間は、神社への参拝は控えるとされている期間ですから、たとえ厄払いでも控える方がいいでしょう。
【忌中・喪中の厄払いは?】
- 忌明け後に神社で厄払いをしてもらう
- お寺で厄除けをしてもらう
- やむを得ない理由がある場合には、神社に相談する
厄除けと厄払いの違いは?
厄除け(やくよけ)や厄払い(やくばらい)は同義で使いがちですが、別なものです。
厄除けとは?
厄除けは、主に寺院で受ける祈祷です。
清めた体に災厄を寄せ付けないよう祈願するものです。
厄払いとは?
厄払いは、神社で受けるご祈祷です。
自身の中にある災厄や邪気を祓うものです。
厄除け・厄払いに適した時期は?
厄除けや厄払いは、できれば1月7日まで、遅くても節分(2月3日頃)までと言われたりしますが、実際にはいつ受けても構わないものです。いくつもの神社のサイトでもそのように説明されていますし、実際に厄除けや厄払いは年中受けることができます。
旧暦では、節分の翌日である立春(2月4日)から次の年の立春までが、おおよその一年間と考えられていました。
そのため、「厄を落としてから新年を迎えたい」との思いから、立春の前日である節分までに厄除けをするという風習が生まれたとされています。
現代でも、その風習が残り、「できれば1月7日まで、遅くても節分(2月3日頃)まで」など言われているだけなのです。
神社では、年間通して厄除け・厄払いのご祈祷を受けることができます。神職の方がそうおっしゃるのですから、風習に振り回される必要はないのです。
なお、最近は幸先参りをする方も増えているそうです。
【幸先参り(さいさきまいり)とは?】
新年を迎える前に厄を落とすために、前年12月のうちに厄除けのご祈祷を受けること

厄を落としてから新年を、との考え方なら「幸先参り」が妥当な気がします。。。
忌明け後に神社厄払いをしてもらう
上述の通り、厄払いは期間限定ではありません。忌明け後に、落ち着いてから厄払いを受ける方がいいでしょう。
お寺で厄除けをする
忌明けを待っての厄払いでは難しい場合には、寺院で厄除けをしてもらうこともできます。仏教では、死は穢れではありませんので、忌中でも問題ありません。
ただ、上述の通り、神社の厄払いと、寺院の厄除けでは、考え方が異なりますので、理解した上でお願いしましょう。
喪中・忌中期間に神社へお札を返すのは?
忌中期間は、神社への参拝を控えますが、忌明け後は喪中期間でも、神社の参拝に問題はありません。
お札やお守りを返納も、忌明け後に行います。その際に、新しいお札やお守りを授かるといいでしょう。
お札やお守りは初詣の際に、新しいものを受けることが多いでしょうが、必ずしも1年きっかりで返納しなければならないわけでも、新しいものを授からないといけないわけでもありません。忌中期間に、新年を迎え、お焚き上げがあったとしても、カレンダーに合わせる必要はないのです。
神社には「古神札納め所(古神札納所、古神符納所など)」、お寺には「納札所」と呼ばれる場所が設けられています。
喪中・忌中期間の正月飾り、しめ縄、破魔矢は?
忌中はもちろんですが、喪中期間(1年)は、正月飾りは控えます。
しめ縄の交換は、忌中であれば神棚封じを行いますので、年末に交換はできません。忌明け後に、交換します。
忌中期間は、上述の通り神社への参拝は控えます。新年に神社で授かる破魔矢がどうしても必要な場合には、予約できるか、郵送してもらえるかなどを、確認するといいでしょう。
忌明け後であれば、喪中でも神社へ参拝し、新しいものを授かることができます。
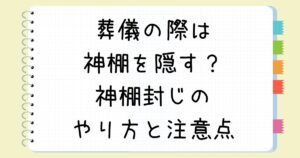
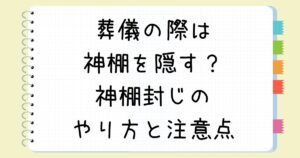
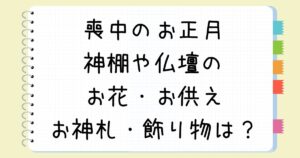
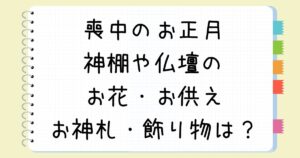
忌中期間にどうしても神社への参拝が必要は場合は?
忌中期間に、どうしても神社への参拝が必要な場合には、参拝する神社に相談してみましょう。
お祓いを受けることで、参拝できる場合もあります。→ 神社本庁HP 服忌(ぶっき)について(https://www.jinjahoncho.or.jp/omairi/gyouji/bukki)
忌明け後は、喪中期間でも基本的には制限はありません。気になる場合には、事前に参拝する予定の神社に確認しておくと安心です。
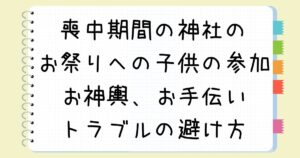
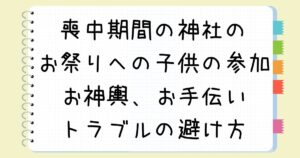
身内が亡くなると、忌中期間は慌ただしく、また悲しみも深いため、初詣や祈願どころではないような気もしますが、これも時代の変化なのでしょうか。
喪中期間といっても、故人との関係性にもよりますが、実生活は1週間程度で戻ることも珍しくありません。家でのお正月の行事は控えても、初詣や祈祷・祈願には行ったり、旅行に行ったり、何かのお祝いに参加したり。。
実生活や気持ちは別として、49日(あるいは50日)でバサっと区切ることに違和感を感じることもあるかもしれませんが、信仰ですから基本的な作法は蔑ろにしないように心がけたいものですね。
神社の参拝に関しては、下記の本が参考になります。滋賀県近江八幡市で1300年続く賀茂神社の第49代宮司の長男である禰宜が書かれた本です。タイトルは過激ですが、内容は極めて穏やかでわかりやすい。すぐ読めます。
Kindle Unlimted 対象。無料で読めます。