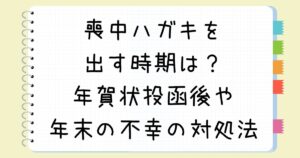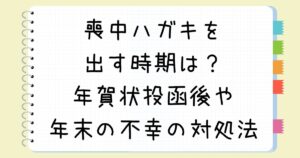弔事というと薄墨というイメージがありますが、喪中はがきの宛名や裏面(本文)などの文字色の基本的な考え方についてまとめておきます。
喪中はがきの宛名や挨拶文(裏面)は黒でなく薄墨?
弔事の薄墨マナーとは?
お葬式(お通夜や告別式など)では、香典袋やお供え物の文字を「薄墨」で書くのがマナーとされていますが、実際どうなのかもう少し掘り下げてみます。
薄墨を使う理由は?
薄墨とは、字の通りですが「墨の色の薄いもの」のことです。通常の墨色よりもグレーに近い色です。
昔は、インクの入ったペンもなかったので、硯ですった墨を筆につけ文字を書いていました。そのため、「突然の訃報を受け、墨をしっかりすることもできず、まだ薄い色の墨で書いて参上した」「悲しみの涙で墨が薄くなった」との意味合いが残され、現代でもお通夜や告別式などの香典袋やお供物には「うす墨」を使う風習があります。
薄墨を使うのはどんな時?
「悲しみの涙で墨が薄くなった」との意味合いから、弔辞全般で薄墨を使うという認識の方もいらっしゃるようですが、薄墨を使うのは、主にお通夜と告別式。初七日までは薄墨を使用することもあります。
これは、お通夜や告別式は、突然の訃報で急いで駆けつける必要がある、しっかり墨をする時間がないからなのです。
喪中はがき裏面の挨拶文は薄墨?
喪中はがきは、身内に不幸があったため、新年の挨拶を欠礼するお知らせです。そのため、遺族側には喪中はがきを用意する時間があるわけですから、濃墨、普通の黒で構わないのです。
ただ、挨拶文が薄墨であれば、受け取った側も弔事があったこと、喪中はがきであることがすぐにわかります。また、「悲しみで色が墨の薄まった」という遺族側の気持ちの表現にもなります。
裏面を印刷する場合には、薄墨か濃墨を選べたり、そもそも薄墨で印刷されることが多いようです。
【喪中ハガキは濃墨? 薄墨?】
- お通夜や告別式で薄墨を使うのは、「突然の訃報で駆けつけた」「悲しみの涙で色が薄くなった」ため
- それより後の法事法要では「前もってわかっている」から濃墨
- 喪中はがきは「前もって用意できる」けれども「悲しみで色が薄まった」から薄墨でも構わない
全部並べると、矛盾もあります。要は、決まり事ではなく、悲しみを表現する風習なのです。
風習なのですから、「人と人との関わりで当然その場面でしかるべきとされる行儀・作法のことを指す」マナーではないのです。白黒はっきりつけられるものでは、ないのです。
喪中はがきの宛名は薄墨?
宛名面は、喪中はがきを送る相手の住所や氏名を記載するのですから、濃墨、普通の黒で、はっきり書くのが基本です。
悲しみの気持ちの表現よりも、確実に郵便物が届くよう宛名をきちんと書くことのほうが優先されます。
【宛名が濃墨・黒の理由は?】
お通夜や告別式の香典袋は、外袋の表書きや名前は薄墨でも、中袋に記載する住所や名前は濃墨、黒で書くとも言われています。これは、遺族側が文字を読みやすいようにとの配慮です。
郵便物(喪中はがき)の宛名も、郵便局員が読みやすいことが大事なのですから、考え方は同じです。

薄墨マナーは、時代にもフィットせず、使いわけにも違和感を感じますが、程よいところで対応するのが一番です。
はがき印刷ソフトの薄墨設定
はがき印刷ソフトによっては、「宛名印刷を薄墨にする・しない」という選択が可能なものもあります。
ただ、プリンター側の問題もありますので、気持ち薄くなる程度で、「薄墨」感がでないことはあります。
喪中はがきの宛名や挨拶文(裏面)に横書きは?
喪中はがきの宛名も裏の挨拶文も縦書きにする、という決まりはありません。最近は、日常的にも横書きが多いため、横書き印刷のものも多数あります。
【喪中ハガキは縦書き?横書き?】
- 裏面の挨拶文が縦書き:表面の宛名も縦書き
- 裏面の挨拶文が横書き:表面の宛名も横書き
これは、単純にバランスの問題です。
ただ、横書きだとカジュアルなイメージになりますし、日本語の文字の流れも縦書きによるものですから、縦書きの方が無難です。特に、年配の方にも喪中はがきを送るのであれば、縦書きにすれば間違いありません。
喪中はがきの宛名は筆ペン?手書きならボールペン、万年筆、サインペン、宛名シールは?
昔は、手書きしか方法がなかったわけですから、手書き当然なわけですが、時代も変わりました。
年配の方でさえ、年賀状はプリンターで出力しているわけですから、喪中はがきもプリンターで出力して何の問題もありません。
【手書きマナーはどこへ?】
宛名印刷も、過去には「失礼だ!」「印刷では心がこもらない」など言われていましたが、現在はマナー講師の先生方も、「宛名は手書き」などとは言いません。時代とともに、マナー講師の先生方の「マナー」なるものも変わるのです。
手書きなら筆ペンがおすすめ
宛名を手書きで書くのであれば、筆ペンがおすすめです。
ただ、これは見た目の印象の問題なだけで、なんの決まり事でもありません。昔は、筆が基本だったこともあり、今でも「毛筆」はペンよりも丁寧、格上なイメージがあるので、それだけの話です。
印刷の時も、明朝体が選ばれるのも、同じ理由です。
筆ペンがない、筆ペンは無理なら?
香典袋の表書きや名前程度ならともかく、喪中はがきの宛名を全部筆ペンで書くのは無理、、、といった場合には、ペンを使っても構いません。
万年筆であれば、筆致もきれいなのでオススメです。
過去には、ボールペンは略式だからNG、サインペンはカジュアルだからNGなど言われていましたが、筆記用具の進化は素晴らしく、チープな感じがしないものもあります。ボールペンやサインペンで書く場合には、インクが変に滲んだりしない、安っぽい印象にならない、書きやすいものを選びましょう。
筆ペンや万年筆がいいのは、筆致が美しいため、丁寧な印象があるからです。あくまで印象の話で、本当に丁寧かどうかは別問題です。丁寧最強であれば、プリントアウトした宛名など、手抜きの極地で許されるものではないはずです。



マナーサイトなどでは、ボールペンやサインペンはマナー違反としながらも、筆ペンや万年筆がなければ使ってもOKなどとあります。本当にマナー違反なのであれば、喪中はがきは緊急ではありませんので、筆ペンや万年筆を購入し用意するべきと言えばいいのに、そこまでは言わないようですね、、不思議です。
【筆ペンはそんなに格上?】
筆ペンの歴史は50年程度です。
筆ペンの発明は1972年のセーラー万年筆「ふでぺん」によるもの。毛筆の次に格が高いという方もいらっしゃるようですが、50年程度の歴史ですから、あまり惑わされないようにしましょう。
宛名シールは?
大量に送付したい時、何度も同じところに送付する時などは、宛名シールは便利ですね。でも、喪中はがきで使用するのは避ける方が無難です。これも、あくまで印象、イメージの問題です。
*****
喪中はがきの場合、表面の宛名も、裏面の挨拶文も、濃墨、普通の黒で問題はありません。
宛名を手書きする場合には、筆ペンがいいと言われていますが、これも決まり事でもマナーでもありません。大切なことは、間違いなくお届けできるようわかりやすい文字で書くことです。
風習と「マナー」は別物です。本来、マナーとは「人と人との関わりでその場面でしかるべきとされる行儀・作法のことを指す」ものです。中には、本当に大切なマナーもありますが、昨今「マナー」と称される細かなルールには、根拠がないものも多数あります。過去にはそうであっても、現代生活にフィットしないもの、時代とともに変化するものもあります。
「マナー」は大切ですが、形ばかりを追いかけ、大切な誰かを思いやる心を置き去りにしないよう心がけたいものです。