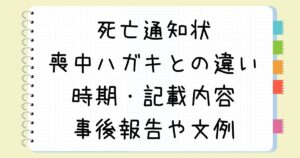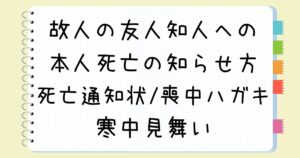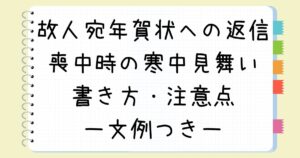喪中ハガキを出す時期や、12月に入ってからの身内の不幸があった場合の対応をまとめておきます。
喪中はがきを出す時期は?いつからいつまでに?
喪中はがきは「身内を亡くし悲しみが深く、新年を祝う気持ちになれないため、年始のご挨拶をせずに失礼します」という、年賀状や年始の挨拶の欠礼をお知らせするものです。
出す時期などに明確な決まりはありませんが、出すにの適切なタイミングはあります。故人の死を知らせる「死亡通知状」とは別のものですから、早すぎるのもよくありません。あくまで、年始の挨拶の欠礼をお知らせするものだからです。
【喪中ハガキを出す時期は?】
喪中はがきは、11月上旬から12月上旬に出すのが、一般的です。
郵便局や書店などで喪中はがきの販売が始まるのは、10月1日です。
10月に入ったら、準備を始めて、10月下旬くらいから発送する方もいらっしゃるようですが、実際には11月中旬〜12月上旬が多いようです。
また、郵便局の年賀状受付開始日である12月15日以降に届くのも、あまりよろしくは ありません。相手方が、年賀状の用意をする前、せめて投函する前に、お知らせする方がいいでしょう。
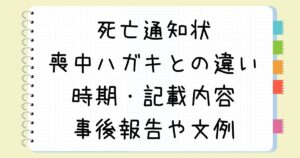
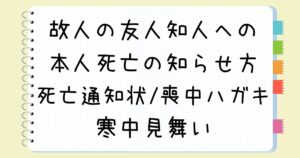
12月に亡くなった場合の喪中はがきは?
12月に不幸があると、葬儀などで慌ただしく、悲しみもまだ深い頃ではありますが、間に合うのであれば喪中はがきを送る方がいいでしょう。
上述の通り、喪中はがきは、新年挨拶を欠礼するお知らせであり、こちらの都合で出すものです。年始の挨拶を欠礼するのは遺族側であり、相手方ではないのです。
相手方が、すでに年賀状を投函した後だとしても、問題はありませんし、遺族側はそこをあまり気にする必要もありません。
ただ、相手方に気を遣い、喪中はがきを出さずに年明けに寒中見舞いを送るという考え方もあります。年末に喪中はがきを受け取った相手方が、年賀状を投函済みの場合、「喪中の人に年賀状を送ってしまった」と気を揉むから、、との理由からです。
どちらが正解というものではありません。亡くなられた日にちや、遺族側で対応できるか、故人との関係性などで判断するといいでしょう。
12月下旬や年末の不幸で喪中はがきが間に合わない場合には?
12月下旬〜年末に不幸があった場合は、喪中はがきを年内に用意することは間に合いません。1月中旬から下旬に寒中見舞いはがきが届くように準備しましょう。
寒中見舞いは、年が明け、松の内(1月7日、地域によっては15日)の翌日から立春(2月4日)までに届けます。地域差もありますので、1月15日以降1月下旬までに発送すれば、間違いないでしょう。
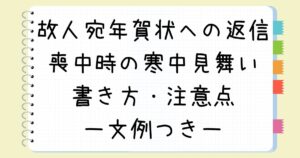
寒中見舞いによる喪中欠礼文例(自分が喪中)
自分が喪中の場合の、寒中見舞いはがきでの喪中欠礼の一般的な文例です。
寒中お見舞い申し上げます
年頭にご丁寧な年始状を頂きまして有難うございました
昨年十二月○○(続柄)○○(故人の名前)が他界し 喪中につき年頭のご挨拶を控えさせていただきました
旧年中にこちらから欠礼のお知らせを差し上げるべきところ 年を越してしまい大変失礼いたしました
本年もどうぞ変わらぬご厚誼の程宜しくお願い申し上げます
厳寒の折 風邪などお召しになられませぬようご自愛くださいませ
令和○年○月
下記のように、故人の詳細(名前、年齢など)を省略しても構いません。
寒中お見舞い申し上げます
このたびはご丁寧なお年賀のご挨拶をいただきましてありがとうございました
皆様ご健勝でお過ごしとのご様子 なによりとお喜び申し上げます
私どもでは昨年○月に○(続柄)が亡くなり 年頭のご挨拶を差し控え失礼いたしました
年末のことでしたので、ご通知が遅れましたことをお許しください
本年も○○様にとりまして、ご健康で実り多い一年となりますようお祈り申し上げます
令和○年○月
年賀状を出した後に不幸があったら?(自分が喪中)
年賀状の配達前であれば、郵便局に取戻し請求を行い配達を取りやめることできますが、タイミングや郵便局によっては難しいこともあります。まずは、近隣の郵便局に聞いてみるといいでしょう。
ただ、不幸があったばかりでは、遺族も慌ただしく、悲しみも深いため、それどころでないこともあります。また、年賀状投函後の不幸は不可抗力なのですから、社会通念上許容の範囲です。受け取った相手方もうるさいことを言わないでしょうし、遺族側も気にする必要はありません。
故人やご遺族とお付き合いが深い方であれば、お葬式の連絡を入れることもあるでしょうし、家族葬などの場合でもお電話などで連絡を入れておいてもいいでしょう。
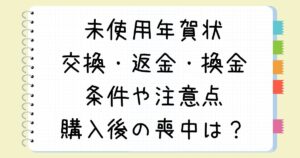
年末に不幸があった場合、翌年は喪中はがき?それとも年賀状?
年末に不幸があった場合は、基本的に翌年の喪中はがき(年賀挨拶の欠礼)は不要と考えられます。
年内にお葬式(通夜、葬儀、告別式など)が済んでいる場合には悩みませんが、亡くなった日によってはお葬式は年を越します。お葬式が年を越しても、命日は年内ですから服喪期間は明けていると、考えて構いません。
過去には、法令で服喪期間が定められていました。最も長いのが父母で、その服喪期間は13ヶ月でした。現在は、その法令は撤廃されていますし、一周忌(一年間)までを喪中とするのが一般的です。
例えば、2023年12月31日が命日であれば、2024年12月31日が一周忌ですから、その翌日の2025年1月1日には服喪期間はあけていると考えられます。
ただ、遺族の悲しみが深い、服喪期間中に年賀状を用意することに抵抗がある場合には、喪中はがきを出しても問題はありません。これは、家族で話し合って判断するといいでしょう。
なお、喪中はがきを出す場合には、故人の名前、続柄、年齢(数え年)などを記載しますが、記載を省略しても構いません。
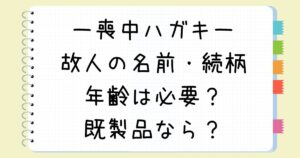
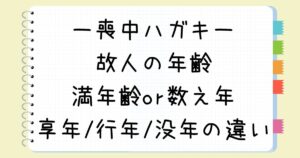
身内に不幸があった場合、喪中ハガキを贈る時期の考え方をまとめておきます。
- 年内に身内の不幸があった場合
11月頃に喪中欠礼(喪中はがき)を送ります
年賀状の投函開始12月15日までに届くよう準備するのがひとつの目安です - 12月中旬以降に不幸があった場合
無理をせずに、年明け1月中旬〜下旬に寒中見舞いのはがきにて喪中欠礼をお伝えして構いません - 年賀状投函後に不幸があった場合
不可抗力ですから、気にする必要はありません
正月が明けてから、死亡通知状などでご連絡します - 年末に不幸があった場合
翌年の喪中ハガキは基本的に不要