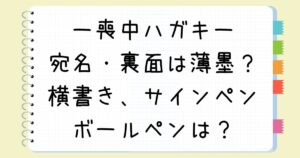配偶者の祖父母が亡くなった場合の、喪中ハガキの書き方や考え方をまとめておきます。
続柄の書き方、差出人を夫婦連名にするのか、夫婦別に出してもいいのか、そもそも喪中ハガキが必要なのか、、働き方や家族の関わり方も変化していますので、唯一の正解はありません。
一般的な考え方をもとに、それぞれ判断する必要があります。
配偶者の祖父母が亡くなったら喪中はがき?
喪中はがきを出す範囲には、決まりはありません。
一般に、喪中の範囲は2親等、つまり、祖父母、親、子、孫、兄弟姉妹及びそれぞれの配偶者と考えます。
ただ、同居していない2親等(祖父母、孫、兄弟姉妹、それぞれの配偶者)の場合には、年賀状を出しても問題ないとされています。
「喪に服す」とは、「悲しみが深いためお祝いをする気持ちになれない」ことを意味します。同居か別居か、何親等かではなく、あくまで自分や配偶者の気持ちの問題なのです。
配偶者の祖父母と同居していた場合、配偶者の親にとっては1親等であり、喪に服しているわけです。自分たちから見れば2親等でも、喪中はがきの方がいいでしょう。同居していなければ、一つ屋根の下の話ではありませんので、故人との関係性や配偶者の気持ちから判断していいでしょう。
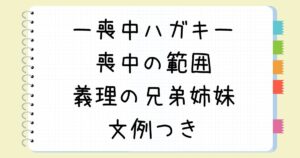
喪中はがきは夫婦別でもいいの?
配偶者の祖父母は、姻族(配偶者の血族)であっても、自分にとっては血族ではありません。
離れて暮らしていて、お会いしたこともほとんどない場合には、日常生活の中でも「喪に服す」感じがないこともあるでしょう。そうでなくても、社会生活の変化から、喪に服す期間自体が、数ヶ月と短くなっているのですから、尚更です。
上述の通り、喪中はがきを出す範囲には決まり事はありません。つまり、唯一無二の正解がないわけですから、自分たちで判断していいのです。いくつかのパターンがありますので、それぞれ解説します。
・喪中はがきを夫婦連名で出す
・喪中にせず年賀状を出す
・喪中はがきと年賀状を使い分ける
喪中はがきを夫婦連名で出す
配偶者の祖父母であっても、2親等です。夫婦連名で喪中はがきを出すことは、一番面倒のない方法です。
喪中にせず年賀状を出す
そもそもで、喪中にせず年賀状を出しても、構いません。
ただ、故人と血縁関係のある親族には年賀状を送らない程度の配慮はしましょう。
例えば、妻の祖父が亡くなったのであれば、妻側の親戚に年賀状を送ることは避けます。
喪中はがきと年賀状を使い分ける
喪中はがきを出すことで、受け取った相手側に気遣いをさせることを避けるために、相手によって使い分けるケースも増えています。
他にも、仕事の関係者など、あまりプライベートな情報を持ち込みたくない場合には、喪中はがきではなく、通常通り年賀状を出すこともあります。
例えば、妻側の祖父が亡くなった場合
- 妻の個人的な関係者には喪中はがきを出す
- 夫の会社関係などは年賀状を出す
- 夫婦でお付き合いのある相手には、年賀状か喪中はがきを出す
喪中はがきと年賀状を使い分けるほどに、相手に気を遣うべきなのかどうかも含めて、あなた方自身の判断です。
喪中はがきは、自分が喪中であり年賀状の欠礼をお知らせするものです。喪中はがきを出す相手方全てが、あなたの親族が亡くなったことを既に知っているわけではありません。
そのため、喪中はがきが届いたことで、近親者が亡くなったことを知り、お悔やみを送っていただくようなこともあるのです。そのような気遣いを避けるためにも、故人と面識がなく、亡くなったことを知らない相手には、喪中はがきを出さないというのは、現代的な考え方とも言えるでしょう。
夫婦連名なら、故人との俗柄の表記は?文例は?
喪中はがきの一般的な文例です。
喪中はがきの一般的な文例
喪中につき年末年始のご挨拶ご遠慮申し上げます
○月に(続柄)(故人の名前)が ○○歳にて永眠いたしました
本年中に賜りましたご厚情を深謝いたしますと共に
明年も変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます
なお向寒の折から皆様にはご自愛のほどお祈りいたします
令和○年 ○月
天寿を全うした場合の一般的な文例
喪中のため新年のご挨拶は失礼いたします
本年 ○月に(続柄)(故人の名前)が享年○○にて天寿を全ういたしました
生前皆様より賜りましたご厚情に深く感謝いたしますとともに
明年も変わらぬご交誼のほどお願い申し上げます
令和○年 ○月
喪中はがきの差出人と、故人との関係を明確にするためにも、続柄、名前、年齢(数え年)を入れるケースが多いです。年齢は「享年○○」でも「○歳」でも構いませんし、記載しなくても構いません。
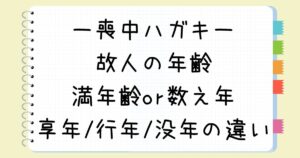
夫婦連名なら祖父母の続柄の表記は?
続柄は、一般的には、世帯主(夫)から見た続柄で記載します。
【続柄の書き方】
- 夫の父母:「父 ○○」「母 ○○」
- 妻の父母:「義父 ○○ ○○」または「岳父(がくふ) ○○ ○○」、「義母 ○○ ○○」または「丈母(じょうぼ) ○○ ○○」
※ 岳父というのは夫から見た妻の父親の敬称、丈母は夫から見た妻の母親の敬称ですが、最近はあまり使わないかもしれません - 夫の祖母:「祖父 ○○」「祖母 ○○」
- 妻の祖母:「義祖父 ○○」「義祖母 ○○」
続柄、名前、年齢(数え年)も記載しますが、細かいことを知らせたくない場合は、故人の情報を記載しなくても構いません。
ただ、続柄は入れておく方がいいでしょう。差出人との関係がわからないと、受け取った相手が心配することもあります。
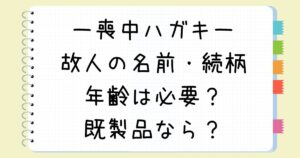
「義」をつけるのが嫌な場合は?
配偶者の親族でも「義」を使わず、「父」「母」「祖父」「祖母」と表記することもあります。これも特に決まり事ではありません。
夫側の親族が、表記にうるさい場合には、気をつける(避ける)方がいいでしょう。。
祖父母が亡くなった場合、喪中はがきを出すかどうかの判断基準のひとつが、「同居」か「別居」かです。
ただ、喪に服すのは気持ちの問題ですから、そこに決まり事はありません。仕事の関係など、あまりプライベートな情報を持ち込みたくない場合には、喪中はがきではなく、通常通り年賀状を出しても問題はありません。年賀状を出しても、お正月の行事はしないで、故人を偲び静かに過ごしてもいいのです。