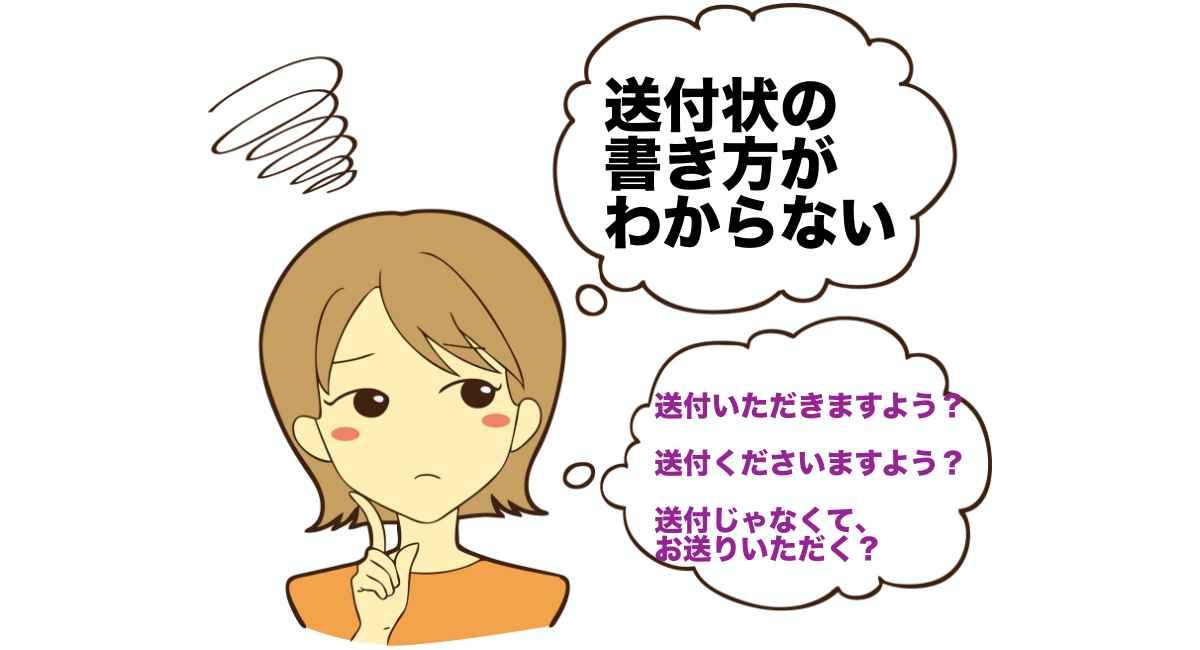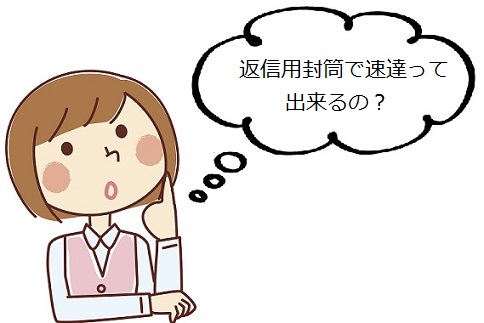資料などもメール送付や、サイトなどからダウンロードできるようになり便利になりました。便利になった分、先方から書面を返送してもらう「返信用封筒」など使う機会も激減し、稀に必要になるとアタフタするのは私だけではないかと思います。
・返信用封筒の宛名の最後は、行と宛どちらにするのか?
・返信用封筒の差出人に相手の名前を書いておくべきか?
・返信用封筒の切手の料金はどうする?
・返信用封筒の入れ方に決まりはある?
今回は、返送用封筒のマナーでよくある悩みをまとめました。作業ですから、必要以上に気を遣う必要はありませんので、大丈夫。安心してくださいね。
返信用封筒の宛先(自分の名前)につけるのは行と宛どっち?

返信用封筒の宛先欄には、団体(社名や部署名)・個人名(自分の氏名)の後ろに「行」を書き加えます。
・団体名・氏名よりも少し小さい文字にする
・団体名・氏名と「行」を少しずらす(縦書きの場合は左寄りに、横書きの場合は下寄りに)、あるいは大きめのスペースを空ける
→ 宛先の氏名と区別をするためでもあります。例えば、名前が弘行さんだと、弘さん宛なのか、弘行さん宛なのかわかりにくいのです。
「宛」はダメ、どちらでもいい、団体なら「行」・個人名宛なら「宛」などいくつかの説もありますが、「行」であれば、まず間違いはありません。
「宛」は、送付状の文面中や、会話の中で「○○宛にお送り下さい」という形で使います
通常は「行」をつけるのですが、最近では次のような考え方もあるようです。
- 返信先の宛名(氏名)には何もつけない
- 返信先の宛名(氏名)に「様」や「御中」を書き加える
- 返信先の宛名(氏名)に「殿」を書き加える
3. の「殿」に関しては、論外ですが、1. と2. に関しては、時代の変化というか、現代ならではの新しい気遣い方、相手への配慮から考えられた行為のようです。
- 行・宛をどうせ消すのだから、何も書かない方が楽だし、先方の手間も減って親切
- 行・宛を決して、「様」や「御中」を書き加えるのだから、最初から書いておけば先方の手間要らずでさらに親切
返信用封筒に、宛名(自分の住所氏名)を記載すること自体が、相手の手を煩わせないための気遣いから来ているものです。だからといって、その宛先である自分に「様」という敬称をつける行為は、自分の行動に尊敬語をつけることと同じです。「私はあなたよりも立場が上ですよ」と同意です。「させていただく」を頻発する現代の言葉遣いとしてはおかしな話です。
「相手を立てて自分がへりくだる」という心から尊敬語や謙譲語は存在します。相手への敬意であり、相手を思う気持ちです。返送先の宛名を記入しておくのも、相手に対する配慮です。
多忙、情報過多、効率重視、検索すれば一瞬で回答される現代では、コトの本質を理解することなく回答ばかりを追いかけてしまうのかもしれませんね。だから、尊敬語や謙譲語、立場には配慮せず、効率だけを重視すると「『様』を最初から書いてあげた方が親切じゃない?」という考えになってしまうのでしょう。時代の流れと共に、どこかのマナー講師が「自分の名前に様をつけるのがマナー」などいう日が来るかもしれませんし、そういった情報を拾ったGPTがそのように答える日が来るのかもしれませんが、少なくても相手に敬意を払うという点では、自分の氏名に「様」「殿」といった敬称をつかうことはありえないことは、頭のどこかに留めておいてくださいね。
なお、返信相手が自社の社長など立場が上の人宛だとしても、返信先の宛名に「殿」を記入しておくことはありません。たとえ社長でも会社であれば身内です。もちろん、先方が「行」を消して「殿」と記載することはありますが。。
こちらもCHECK
-

-
返信用封筒「行」の二重線は縦横斜め?横書きなら?様・御中?差出人名・封の〆は必要?
同封されている返信用封筒で返送する場合、多くの場合に宛先が「行」となっているため、この文字を二重線で消して「様」か「御中」を書きます。 ・「行」を消す重線は縦横斜めどれでしょうか?・縦書き横書きで消し ...
続きを見る
こちらもCHECK
-

-
返信用封筒の送付状書き方は?いただきますよう?くださいますよう?
「契約書2部を取引先に送って 、1部返送してもらって下さい。」 会社の業務で上司からこのような指示をされた際、契約書だけでなく返信用封筒や送付状を添えることが大切です。 今回は、返信用封筒を添えて送る ...
続きを見る
返信用封筒の差出人欄に相手の名を書く?
返信用封筒の差出人は相手方ですが、差出人名や住所はこちらで記入する必要はありません
差出人名を記入する必要がない理由はいくつかあります。
- 返信用封筒の宛先をこちらで記入しているため、宛所不明などで差出人(相手方)に返送される可能性は低い
- 差出人が会社の場合、差出人記載のルールや、担当部署などの変更の可能性もある
- 相手側の住所氏名をこちらで記入するのは差し出がましく失礼な行為にあたる
いずれにしても、返信用封筒に相手方の住所氏名を記入することは、相手への配慮でも親切にもあたりませんので、ご注意ください
〜 封筒の書き方 〜
【往信用封筒】
◉ 表面:
・相手方の氏名+様
・会社などの担当者宛:所在地、会社名、部署、相手方氏名+様
・会社や部署宛: 会社名/部署名+ 御中 、あるいは 会社名/部署名+ ご担当者様
◉ 裏面:
・自分の住所、氏名
・会社場合は所在地、会社名、部署、氏名
【返信用封筒】
◉ 表面:
・自分の住所、氏名+行
・会社の場合には所在地、会社名、部署、氏名+行
※ 「行」は氏名よりも少し小さな文字で、縦書きなら少し左に、横書きなら少し下にずらす、あるいは名前と間に大きめのスペースをとります
◉ 裏面:記入なし
後払いや着払いでない場合には、返信用封筒には基本的には切手を貼ります
返信用封筒には切手は貼る?
後払いや着払いでない場合には、返信用封筒には基本的には切手を貼ります
これは、返信をお願いしている相手方に対して、「必要な書類をこの封筒に入れて、ポストに入れていただくだけで結構です」という配慮です。「基本的には」というのは、返信が必要がどうかにもよるからです。
こちらからのお願いで返信していただくのであれば、相手方の手を煩わせないためにも切手は必要です。もしくは、後払いや着払いに対応した封筒を利用しましょう。
返信用封筒の切手料金は?
日本国内の場合、料金は封筒の大きさと重さだけで決まる従量制規格です。
返信用封筒に入る書類のおおよその重さ(書類何枚かなど)から、郵便料金を確認し切手を貼ります。下記料金は、2023年7月現在の料金です。
(1)定型郵便物:23.5cm×12cm以内、厚み1cm以内
・25g以内:84円
・25g超50g以内:94円
・50g超:定形外料金と同じ
(2)定形外郵便物(規格内):34cm×25cm×3cm以内で重さ1kg以内
・50g以内:120円
・50g超100g以内:140円
・100g超150g以内:210円
・150g超250g以内:250円
※ これ以降の重さについても数段階の料金が決まっています
(3)定形外郵便物(規格外):(2)の「規格内」に当てはまらないもの
・50g以内:200円
・50g超100g以内:220円
・100g超150g以内:300円
・150g超250g以内:350円
※ これ以降の重さについても数段階の料金が決まっています
こちらもCHECK
-

-
返信用封筒を速達で出してもらう方法は?書き方や同封添え状は?
同封した返信用封筒で、相手に速達で出してもらうには、どのように返信用封筒に書いたらいいのでしょうか。 同封する添え状で失礼のない書き方はあるのでしょうか。 速達のマナーはあるのでしょうか。 今回は、返 ...
続きを見る
返送用封筒の切手料金が不足したらどうなる?
切手料金が不足した場合の郵便局の対応は、以下のいずれかになります。
・受取人に届く前に差出人に返送される
・受取人に届いて不足額を支払う
・受取人が不在だったり、支払いを拒否したりすると差出人に返送される
参照:日本郵便 手紙にまつわるQ&A
差し戻されず、受取人(変信用封筒の宛先である自分)に届けば、不足分を支払えば済みますが、差出人である相手方に差し戻されてしまうと、相手方が不足料金を支払い再度投函するという二度手間になりますし、返信封筒が届くまで時間もかかりますし、相手によっては面倒でしかないため返信してもらえない可能性もあります。
なんにもいいことはありませんので、料金不足にだけは気をつけましょう。
返信用封筒の切手料金の確認の仕方
特に決まりはありませんが、手順として決めておくと確認忘れがなくなります。
1. 封筒の大きさが定型か、定形外かの確認
2.返信用封筒に入るものを想定して計量
・返信用封筒+返信してもらう内容物+A4コピー用紙1枚分(相手方からの送付状や予備)
3.該当する料金の切手を貼る
・全体の重さが料金設定の境界に近い場合には、1段階上の料金分の切手を貼っておくと安心です
返信用封筒の入れ方は?
返信用封筒は、相手が取り出しやすく、わかりやすいように入れるのが基本です。
自分宛に送ってもらうための封筒ですから、折って構いません。送る封筒にピッチリで入っていると取り出しにくいですし、開封するときに返信用封筒を切ってしまう、破いてしまうなど破損しやすくなります。
◉ 返信用封筒であるとわかりやすいように入れる
・返信用封筒の宛名(自分の名前)を外側にして折る
◉ 相手側が取り出しやすいような入れ方をする
・送る封筒の開封口に近いところに来ないよう、奥(下)の方に入れる
・送る封筒と、返信用封筒が同じサイズの場合には、2つ折りか3つ折りにする
・返信用封筒に切手を貼った場合には、ノリや水分が乾いてから入れる(中でくっついて取り出しにくくなるのは避けましょう)
さいごに
返信用封筒の宛名には「行」をつけます。時代の流れともに、今後変わっていく可能性もありますが、個人名であれば「行」、会社や部署など団体宛の場合には「御中」と覚えておけば間違いありません。
また、切手はくれぐれも料金不足にならないよう、きちんとレタースケール(郵便はかり)で量って、料金を確認してから貼りましょう。