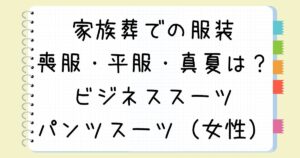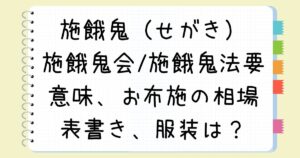家族や故人のごく親しい友人などだけで、故人のお見送りをする「家族葬」は、社会生活の変化、葬儀費用の高騰などの理由から、この数年注目を集め、増加傾向にあります。
「家族葬」というくらいですから、参列するのは家族が中心となりますが、どの程度列席者を呼ぶか、どのような内容で行うかなどの明確な定義はありません。故人や遺族の意向でその範囲や内容を決めるため自由度が高い一方で、判断が難しいことも考えられます。葬儀後にトラブルにならないための、基本的な考え方や注意点をまとめておきます。
家族葬の「家族」の範囲はどこまで?
家族葬の「家族」の範囲には明確な定義はありません。故人や遺族の意向で、その範囲を決めることができます。
家族葬とは?
家族葬とは、家族や故人のごく親しい友人などだけで、故人のお見送りをすることです。
明確な定義はありませんが、公正取引委員会が暫定的に定めている定義(2016年)では、親族や親しいご友人など親しい関係者のみが出席して執り行う、列席者50名未満の葬儀を家族葬としています。
【家族葬】
参照:(平成29年3月22日)葬儀の取引に関する実態調査報告書 PDFの27ページ
親族や親しい友人など親しい関係者のみが出席して執り行う葬儀。通夜・告別式,火葬等は一般葬と同様に執り行われる。
※ 本調査においては,参列者50名未満の葬儀を家族葬と定義した。
10人程度の家族葬なら範囲は2等親
故人と二等身以内で家族葬を行う場合には10人程度で営むことができます。
【二等親以内の親族とは?】
故人の配偶者、親(一等親)、子(一等親)、祖父母(二等親)、兄弟姉妹(二等親)、孫(二等親)、それぞれの配偶者
兄弟姉妹、子や孫が多い場合には、二等親以内の親族といっても10名を超えることもあるでしょうし、極端な話2〜3名で営むこともできます。二等親以内の親族と、ごく親しい友人だけに列席していただくこともできます。
故人が自分の親の場合、親の兄弟、自分にとっての叔父叔母までは範囲に含まれますので、最小限の範囲と言えます。
10~30名程度の家族葬なら範囲は親戚+ごく親しい関係者
遺族に加え、親戚やごく親しい友人や仕事などの関係者などに列席していただくと、10〜30名程度になるでしょう。
遺族も、ほぼ全員が面識があるような感じです。家族葬でも一番多いパターンとも言われています。
30〜50名程度の家族葬なら範囲は親戚+友人や親しい関係者
親戚の他にも、親しい友人や、仕事やプライベートの活動で関係の深かった関係者などに列席していただくと、30名を超えることもあるでしょう。
交友関係の広さや、親戚の数にもよりますが、故人と関わりの深い方には一通り声をかけることができそうです。故人と親しくしていた方が「参列できなかった」というトラブルは回避できるでしょうが、故人や遺族の意向以上に葬儀日程が広く伝わる可能性が高くなり、お声がけしていない方が当日列席されるといったトラブルが起きやすくなるかもしれません。
家族葬の参列者の範囲で迷った時の判断基準は?
遺族が参列者の範囲を決めないと、葬儀の準備が進まなくなります。
また、亡くなったことが親族や近所の人などの耳に入ってしまうと、そこから遺族の管理できない範囲に訃報は広まるものです。訃報が広まってしまった後では、家族葬をするので参列や香典、供物、弔問を辞退するというのは、なかなか言いづらいものです。
遺族個々人にも、それぞれの想いや希望するお別れの形があるかもしれませんが、家族葬をする場合には、早急に判断する必要があるのです。
迷った場合の判断基準は、2つです。悲しみにくれているところに辛い判断ではありますが、割り切って考えることをお勧めします。
【家族葬を営むためのポイント】
- 二等親以内に限定する
- 迷った相手には参列の案内をする
- 案内をした方には「家族葬」であることを明確に伝える
二等身以内に限定する
一般葬ではなく、家族葬で営むと決めた場合で、どこまでの範囲とするか悩んでしまったら、二親等以内に限定されるケースが多いようです。
二等親であれば、上述のように「故人の配偶者、親、子、祖父母、兄弟姉妹、孫」ですから、まさに「家族」です。
「故人の遺志により家族のみで執り行う」という説明もつきますので、不要なトラブルを回避し、周りの理解を得やすくなります。
親族や関係者には、訃報は早めに連絡すべきものですが、家族のみで葬儀を営む場合には葬儀終了後にお知らせしてもいいでしょう。
迷った相手には参列の案内をする
家族葬とはいえ、親戚やごく親しい関係者にも参列していただく場合には、故人がすでに決めている場合を除けば、遺族がその範囲を判断することになります。
人数にもよりますが、判断に悩む場合には葬儀の案内をするのが無難です。故人との最後のお別れですから、葬儀終了後には取り返しがつきません。判断に悩むくらいであれば、列席いただく方が後悔しないでしょう。
案内をした方には「家族葬」であることを明確に伝える
葬儀の案内をした方には、「家族葬」を営むことを明確に伝える必要があります。
言い方を変えれば、「口止め」のようなものです。故人が死去したことが広がった後では、当日や後日のトラブルに繋がりかねません。
家族葬のトラブルを避けるための連絡方法
家族葬では、一般葬にはないトラブルが発生しやすくなります。
トラブルを回避する最大の対処法は「明確な連絡」につきます。
【連絡は明確に】
- 訃報の連絡をする相手を限定する
- 列席者には家族葬であることとその範囲を明確に伝える
- 事後報告〜必ずしも葬儀前に訃報の連絡をする必要はない
葬儀前に訃報の連絡をする相手を限定する
訃報は早急に連絡するのが基本ですが、家族葬の場合には葬儀前に連絡する範囲や内容を限定し、家族間で明確にしておくといいでしょう。
まずは、家族や近親者の中で家族葬であることを理解することが大切です。家族や近親者から他の人へ訃報が伝わった際に、「家族葬」であることも伝えなければ、弔問や葬儀日程の問い合わせがあったり、弔電、香典、供物などが届くこともあります。悪意があるわけではなく、訃報とはそういうものですから、仕方がありません。
一度広まってしまうと、その範囲は家族で管理できなくなりますので、そこから家族葬であることを伝え理解していただくのには、かなりの労力が必要です。家族を失い悲しみの中、家族葬への理解をいただくよう周りに説明するのは、酷なことです。そうならないためにも、訃報の連絡する相手や、連絡内容を限定しておくといいでしょう。
参列者には家族葬であることとその範囲を明確に伝える
家族葬に列席していただく親族や関係者には、葬儀の案内の際に、「家族葬」であることを明確に伝え、理解していただきましょう。
親族であれば何等親までか範囲を明確にし、友人や関係者であれば「友人代表として○○様だけ / ほんの数名だけ」と限定であることや、葬儀の案内をしていない方には葬儀後に遺族側からきちんとご報告することを、葬儀の案内とともにお知らせするといいでしょう。
葬儀の案内の時点で明確にお伝えし理解していただくことで、その方から訃報が広まることも回避できます。訃報のお知らせをした範囲を遺族が把握していれば、葬儀当日に急な参列者が来るなどのトラブルも避けやすくなります。
勤務先には、忌引き休暇の申請が必要になります。「家族葬」であること、弔問の辞退を伝えておけば、基本的に問題になることはありません。
事後報告〜必ずしも葬儀前に訃報の連絡をする必要はない
限られた範囲で家族葬を執り行う場合には、列席者以外の方へは必ずしも葬儀前に訃報を連絡をする必要はありません。
本来、訃報は他界後早急に連絡するものではありますが、家族葬の場合トラブルを回避するためにも、葬儀後に「死亡通知状(死亡通知はがき、訃報はがき)」といった形で、お知らせすることもできます。
葬儀後も、弔問や香典、供物等を辞退する場合には、「死亡通知状(死亡通知はがき、訃報はがき)」にその旨を明記すれば理解は得られるでしょう。
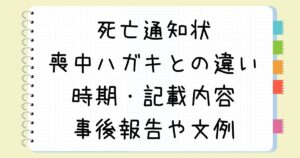
家族葬の日程調整でのトラブル予防〜友引での葬式は?
友引には葬式(葬儀・告別式)をしてはいけない、避けるべきとの説もありますが、家族葬でも避けるべきかどうかの考えかたも記しておきます。
家族葬は友引にしてもいい?
友引に葬儀をすると「友が引かれる」=「友を死後の世界へ引き寄せる」ため避けるべきではないかと言われますが、コレは迷信的なものであり、実際に葬儀を執り行っても問題ありません。
葬式(通夜・葬儀・告別式)に友引は関係ない
「友引」は、元々は中国の勝負の世界が原義があり、勝負の決着がつかず共に引いた「共引き」の意味があります。勝負の決着がつかない良くも悪くもないとされる日なのです。
日本で「友引」となったのは、陰陽道の「友引日」と混同されたとも考えられています。陰陽道での「友引日」とは、「ある日ある方向に事を行うと災いが友に及ぶ」(参照:wikipedia)とされる日のこと。いずれにしても、仏教的な意味合いは一切ありません。
葬儀・告別式ができない理由は火葬場が休業日?
「友引に葬式(葬儀・告別式)をするのは縁起が悪い」というのは、俗説・迷信でありますが、友引を休業日としている火葬場が多くあります。
火葬場が休業、つまりその日に火葬できないため、別の日に葬儀や告別式を営むことになります。
友引だから葬儀や告別式ができない(しない)のではなく、火葬場が休業日だから葬儀や告別式ができなかった、、、ということなのです。
火葬場が、迷信や俗説を信じて休業しているわけではありません。俗説や迷信を信じている人が一定数いることや、信じてはいないけど面倒は嫌だからなんとなく避ける人がいるため、友引に葬儀を営むことを避けがちになります。葬儀がない日には、基本的に火葬場の利用はありません。つまり、友引は火葬場の利用数が減る日でもあるので、休業日に設定しているだけの話です。
家族葬だからこそ、迷信も俗説も大切?
友引には火葬場都合で家族葬ができないこともあるのですが、もし火葬できるとしても家族葬の場合には、配慮が必要な場合もあります。
家族葬の場合は、その範囲にもよりますが、基本的に故人の家族や近親者のみで営みます。特に故人の配偶者や親が、六曜を気にされる場合には、友引での家族葬は避けた方がいいでしょう。
トラブルにならない葬儀日程の決め方
葬儀の日程を決めるときには、菩提寺と葬儀社にお任せすると安心です。
火葬場と僧侶のスケジュールから調整し、葬式の日程が決まります。六曜を強く信じる方が近親者などにいるとしても、菩提寺と葬儀社で問題のない日程を決めたとなれば、不要なトラブルを避けられるでしょう。
葬式(通夜・葬儀・告別式)と六曜の関係、注意点は?
六曜とは?
六曜は、鎌倉時代に中国から伝わった暦注(暦に記載される日時や方位などの吉凶、その日の運勢など)が元と伝わります。ただ、中国でも六曜がいつの時代に確立されたのかは不詳。
当時日本には、現代の七曜日にあたるものがありませんでした。旧暦の1ヶ月30日を5つに分け、日を区別するために六曜を使っていました。その名称や解釈、順序は少しずつ変化しています。江戸時代には、根拠のないさまざまな暦注もはやり、信じる人もでてきました。
明治時代に入り旧暦から新暦へ移行する段階で、「吉凶付きの暦は迷信」として政府が禁止したことにより、逆にさらに注目されるようになりました。第二次世界大戦以降、広く普及し現在に至ります。
六曜の種類別と葬式(通夜・葬儀・告別式)との関係は?
六曜は、冠婚葬祭等の儀式を行う日取りを決める際の吉凶判断として利用されることが多いです。
先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6種類がありますが、仏教との関連や根拠もないため、葬式(通夜・葬儀・告別式)の日取りで重視すべきものではありません。ただし、信じている人や、縁起を気にする方もいるので、把握しておいてもいいでしょう。
◉ 先勝(せんしょう・さきがち)
先勝は、六曜の中でも吉日にあたります。午前中が吉、午後二時から六時までは凶であるため、勝負事や急ぎごとは午前中がよいとされています。
葬式(通夜・葬儀・告別式)は、勝負事でも、急ぎごとでもありませんので、葬儀に日取りには配慮不要です。
◉ 友引(ともびき)
友引は、そもそも勝負事が引き分けになる日、「共引」です。陰陽道と混同された結果、現在の「友引」で定着し、「親しい友人を故人が道連れにする」と忌み日とされ、現在でも葬儀や告別式の日取りとしては避けられることもあります。しかし、宗教との関連性はありません。
近年は、気にしない方も増え、共引きでも葬儀や告別式を執り行うこともありますが、火葬場が休業日のことも多く、そもそもで葬儀や告別式ができないこともあります。
◉ 先負(せんぶ・さきまけ)
先負は、午前が凶、午後が吉。何事も控えめにし平静を保ち、勝負事や急ぎごとは避けた方がよいとされています。
葬式(通夜・葬儀・告別式)は、勝負事でも、急ぎごとでもありませんので、葬儀に日取りには配慮不要です。
◉ 仏滅(ぶつめつ)
仏滅は、六曜の中で最も凶の運勢の悪い日とされています。慶事は避けた方がよいとされますが、弔辞には関係ありません。
◉ 大安
大安は、六曜の中で最も運勢の良い日とされます。あらゆることがつつがなく進められるとされ、祝い事や新しいことを始める日に選ばれやすい日ですが、葬式(通夜・葬儀・告別式)との関連性はありません。
◉ 赤口(しゃっく・しゃっこう)
赤口は、午前11時〜午後1時までが吉、それ以外は凶とされ、慶事には不向きとされています。また、「赤」が血を連想させるため、刃物を持つ仕事の人には注意すべき日とされていますが、葬式(通夜・葬儀・告別式)との関連性はありません。
宗教ごとの六曜との関係は?
葬式の形は様々ですが、多くの場合宗教が関わってきます。宗教と六曜の関係も確認しておきましょう。
仏式
日本人の葬式の多くは仏式です。仏教と六曜に関係性はありません。特に、浄土真宗では、迷信に惑わされるのはよくないとの教えから、友引を避ける風習を明確に否定しています。
キリスト教
キリスト教も宗教的には六曜とは無関係です。信仰とは無関係に、地域風習として避けることはあるようです。
神式
神式も主教的には六曜と無関係ですが、地域や生活と密着した祭りごとが行われるため、六曜が意識されることはあるようです。
*****
家族葬の歴史はまだ浅く、20年程度と言われています。
高齢化や葬儀費用の高騰に加え、近年の社会的要因もあり、家族葬を選ぶ遺族が大幅に増加しているようです。年代や地域によっては、理解され難いこともあるかもしれませんが、社会全体としては理解が広がりつつあります。
家族葬には、明確な定義がなく、どこまで葬儀に列席していただくかは、故人の遺志か遺族の意向によります。列席いただく方にも、葬儀の案内をしない方にも理解を得るためには、初期の案内の仕方が極めて重要です。
六曜は、迷信・俗説ではありますが、人々に広く根付いていることも確かです。葬儀や告別式の日取りに影響を与えるのは友引だけです。「故人が親友を道連れにする」との解釈から、忌み日とされ避けられてきました。
本来は、宗教と六曜、葬式と六曜は無関係なので、葬儀や告別式を執り行うことになんの問題もありません。最近では、気にしない方も増えてはいますが、年配者を中心に、「友引に葬儀が避けるべき」と考える方も少なくありません。
家族葬の場合には、関係者が限定されます。その中に、お一人でも気にされる方がいる場合、可能であれば友引での家族葬は避け、日取りを調整することをおすすめします。列席する全ての方が納得した形で、故人との最後のお別れができることが、なによりも大切です。